棒ノ嶺(棒ノ峰・棒ノ折山)の名前の由来
棒ノ峰 東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県飯能市との境にある標高969mの山で、奥多摩と奥武蔵の山域の境にあります。棒ノ嶺は今上天皇が皇太子殿下時代の1986(昭和61)年6月17日午前10時前、埼玉県側
棒ノ峰 東京都西多摩郡奥多摩町と埼玉県飯能市との境にある標高969mの山で、奥多摩と奥武蔵の山域の境にあります。棒ノ嶺は今上天皇が皇太子殿下時代の1986(昭和61)年6月17日午前10時前、埼玉県側
立川通りの『ごはんと喫茶 いい日々』にて、おいしい焼魚定食とコーヒーをいただき、心身ともに満足した私は散歩がてら国立まで歩くことにした。立川通りを東に進んだところで、いい感じの緑道があった。方向的にも

「Coffee Bricks」 JR片倉駅から少し歩いたところ・八王子市片倉町2434にある「Coffee Bricks」は煉瓦造りの喫茶店です。 大正7年(1918)に米蔵として建てられたというこの

湧水にもっと関心を持ってほしい、湧水の保護と回復を図るためとして、東京都が「東京の名湧水57選」を選定したのが平成15年(2003)だった。多摩地域には38の湧水が選定されている。各々のコメントを読ん

11月に入ると、私が住んでいる武蔵野市でも赤く色づき、たわわに実った柿の実を民家の庭先で見かけるようになる。たわわに実り、晩秋の陽光を浴びて赤色に輝く柿の実は、ほほ笑ましく、なんとなく和んだ気分にさせ

稲城市 地図 稲城市は、東京都心の新宿から西南に約25キロメートル離れて位置しており、東西、南北ともに約5.3キロメートル、面積17.97平方キロメートルで、多

町田市には2つ、多摩市には1つの一里塚跡がある。これらは「御尊櫃御成道(ごそんひつおなりみち)」と呼ばれる道筋に建てられている。 御尊櫃御成道 徳川家康は、元和2年(1616)に亡くなると久能山に葬ら

今回のブログは、以前高幡不動尊にお参りした際に境内で「藤蔵・勝五郎生まれ変わり ゆかりの地記念碑」の碑を目にしたことがありましたが、それ以来気になっていた生まれ変わりの話です。 勝五郎生まれ変わりの話
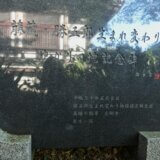
多摩センター駅近くにKDDIのLINK FOREST(複合型宿泊研修施設)が開設されたのが2020年4月。その2Fに日本の国際通信の歴史を解説するKDDI MUSEUMと東山魁夷やエミール・ガレのガラ
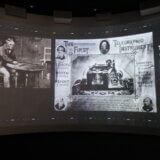
古代・中世・近世・近代・現代とは みなさんは、中世は武士の時代が始まりが「いい国つくる鎌倉幕府」から「いい箱つくる鎌倉幕府」に変わったのをご存じでしょうか。これと同じような論争が江戸時代を示す近世にも

9月の残暑厳しき日、野山北公園自転車道を歩いてみた。野山北公園自転車道は羽村・山口軽便鉄道の廃線跡を、武蔵村山市の区間で、サイクリングロードとして整備した自転車道である。 羽村・山口軽便鉄道 野山北公

青梅の地名の由来になった青梅市の金剛寺にある梅の木 金剛寺 青梅市天ケ瀬にある真言宗豊山派の寺院で青梅山無量寿院と号し、本尊は不動明王です。承平年間(931~938)、寛空(かんくう)上人が創建し

前回7月3日のブログ「武蔵国国府はなぜ府中に置かれたか(703年)? 1300年前の府中の謎を探る」として、現在の東京都と埼玉県並びに川崎・横浜の大部を一国とした武蔵国が、約1300年前の701年の大

日の出町平井の「鹿野(ろくや)大仏」の顔を見たくてJR福生駅西口から武蔵五日市駅行きのバスに乗った(塩沢寶光寺前下車)。鎌倉大仏(11.39m)をしのぐ大きさだけに鹿野大仏の全身が、その名に由来する鹿

はじめに ここでは、より身近な多摩地域のPFAS問題の最新情報をお伝えします。PFAS問題の概略を知りたい方は別ページ「多摩地区のPFASについて」へ 多摩地域の行政の対応 市民団体からの呼びかけ 国
