路線バスで立川市から武蔵野市まで行って来ました
路線バスで立川から新宿まで行ってみたいとかねがね思っていました。 今回は「多摩・武蔵野」ということで、立川駅南口から杉並区との境の地点となる武蔵野市吉祥寺東町(ひがしちょう)まで行って来ました。 立川

路線バスで立川から新宿まで行ってみたいとかねがね思っていました。 今回は「多摩・武蔵野」ということで、立川駅南口から杉並区との境の地点となる武蔵野市吉祥寺東町(ひがしちょう)まで行って来ました。 立川

凹地(窪地)の地図記号 地図記号の中に次のような矢印で示される記号があります。(円弧状の線は等高線) これは国土地理院の地図記号において「凹地(窪地)」を表す記号として使われており、地面の窪んだ部分を

鉄道と道路の交差というとこれは踏切のことですが、あることを発端にして、この踏切に関する法律を知ることとなりました。今回は、そのことを書きます。 その発端というのは、西武新宿線で花小金井-小平間を走行す
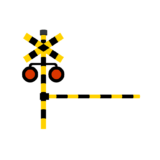
武蔵野八幡宮(武蔵野市吉祥寺東町)の境内に、吉祥寺ウドの由来を述べている案内板が立っている。 江戸時代、武蔵野八幡宮の周辺は畑作農業が盛んで、ウドの栽培も盛んであったという。 日本でウドの栽培が始まっ

新型コロナの「まん延防止等重点措置」の適用地域に関するニュースで、三鷹駅南口は三鷹市、三鷹駅北口は武蔵野市となっており、出口の違いによって規制の内容が違っていて飲食店関係者の当惑のテレビ報道が何度も流

狭い間口で並ぶ店の様子を「まるでハーモニカの吹き口のようだなあ」と文芸評論家の亀井勝一郎がつぶやき、これを覚えていた商店会役員たちがハーモニカ横丁と名付けたとか。 このハーモニカ横丁に入る表の道路、通

先のブログで、かつて武蔵野市に5万人を収容できる「グリーンパーク野球場」と呼ばれる球場があったことを紹介しました。当時、大人数の観客を球場へ輸送するために鉄道も敷かれていました。その鉄道が、「三鷹駅」

武蔵野市の空撮写真を眺めてみると、都立武蔵野中央公園の東隣に、都営住宅などを間に挟んで円を描くように敷設された道路とその道路に囲まれて立ち並ぶビル群が写っています。ビル群はUR都市機構の武蔵野緑町パー

明治・大正期における東京市の水対策 明治から大正期にかけての急速な人口増加により、当時の東京市は生活用水確保のために新たな水源を確保する必要がありました。そこで、東京市は、狭山丘陵に上貯水池と下貯水池

私が暮らす武蔵野市の主要道路の一つに五日市街道があります。その歴史や成り立ちについて気に留めることはあまりなかったのですが、今回の新型コロナによる自粛は思い起こす時間を与えてくれました。 五日市街道は

武蔵野市八幡町に、五日市街道に面して関前八幡神社と延命寺という寺社が並んで建っている。江戸時代この地域は関前村と呼ばれ、開村時の寛文10年(1670)に鎮守八幡神社が創建された。その後明治維新の神仏分

武蔵野市の主要道路の一つ、「中央通り」は武蔵野市をほぼ南北に走り、「千川上水」を横切ると、上水と並んで走る練馬区の道路と交差する。交差点の北側は練馬区である。交差点の名前は「更新橋」。 その交差点の四

ブログとは縁のなかった私ですが、徒然なるままに綴ってみたいと思います。 大正6年(1917)、群馬県出身の中島知久平(1884-1949)という人物が兵器としての航空機に注目し、海軍機関大尉を辞して郷
