文具や家電など昭和レトロの製品が平成生まれのデジタル世代などに「かわいい!」「しんせんっ!」とウケているという。旧青梅街道沿いを中心に青梅駅前とその周辺に吹いているレトロ風に懐かしさと歴史の風格を感じた。
看板に息づく映画の町、甦れ
立川駅発の青梅行き終着、青梅駅のホームから地下通路に降りる。壁面に一世を風靡した映画の手描き看板が連なる。「終着駅」(昭和28年=1953年)、「怪傑黒頭巾」(昭和28-35年)、「旅路」(昭和33年)、「ティファニーで朝食を」(昭和36年)、「鉄道員(ぽっぽや)」(平成7年=1995年)。どれも作品のストーリーが蘇り、主演のポーズや目が絵全体に動きを醸し出している。青梅には3館の映画館があったが、昭和48年(1973)までにすべて廃館になった。

「映画の町へようこそ」といった感じの手描き映画看板
青梅生まれの映画看板師・久保板観(ばんかん)さん(平成30年=2018年逝去)が映画の町だった青梅を盛り上げようと自ら手掛けた多くの映画看板を商店街に掲げて「昭和レトロの町・青梅」に勢いを与えた。映画看板の多くは老朽化して撤去された。
いま、「キネマ通り」の名が残り、今年6月、ミニシアター「シネマネコ」(西分町)が立ち上がった。オープニングにはシネマネコ代表の菊池康弘さんがアニメ映画監督・宮崎駿さんに直訴してスタジオジブリの「猫の恩返し」を上映した。半世紀ぶりの映画館誕生だ。すでに3000人ほどが入館しているという。9月(10~23日)の上映作品は「シェルブールの雨傘」「ヘアスプレー」「ラ・ラ・ランド」を予定している。

間もなく建築後100年を迎える青梅駅舎
青梅沿線の宝 間もなく築100年
駅舎にも大正文化の香りが漂う。青梅駅は沿線各駅に多い現代的な建物ではない。青梅鉄道(JR青梅線の前身)創業30周年を記念して木造平屋建ての駅舎兼本社を大正13年(1924)に建て替えたものだ。前年に起きた関東大震災をきっかけに耐震耐火性に優れた構造を取り入れた。モダニズム建築に至る過渡期の様式で地下室には売店もあったという。元鉄道省建築課長で建築設計士の久野節(みさお)さんが設計した。
駅舎は、間もなく築100年を迎えるが、変わらずに清楚感が漂う。細部にアール・デコ調の装飾が施されているからか。青梅線沿線の宝の一つとして残したいものだ。

昭和ムード漂う町を流すチンドンマン
軽快な音楽奏でて町を流すチンドンマン
駅舎を出たら爽やかで軽快なクラリネットの音が聞こえてきた。芯に響く太鼓と鉦の音も。チンドンマンの鳴り物の音だ。この日、駅前で行われていた「青梅本町朝顔市」のアピールの一環で、チンドンマンは商店街に繰り出していた。鳴り響く昭和歌謡のメロディーはひときわ気持ちを和ませる。これぞ、昭和最大の見世物だ。カメラを向けると「どうぞ、どうぞ、撮ってとって」とにこやかに応じてくれた。来る人来る人がアサガオの鉢を手に下げて帰った。
駅前変わる13階建てマンションの建設進行
駅前通りに面している2棟の大型商業ビルは長年閉ざされているが、ここを中心に老朽化した共同ビルや木造の建物を統合して一帯を再開発する計画がスタートしている。3年後には高さ46mの地上13階建て(地下1階)にファミリー向け住居約110戸や店舗、公共施設などがお目見えする。
路地や街道で猫頼みの町おこし
駅西側の路地を入ると、「にゃにゃまがり」があるそうだ。「にゃにゃ」ってなんだ? 古い木造のこじんまりした住宅、人一人が歩ける程度の路地の頭上に手描きの「昭和の猫町 にゃにゃまがり」の看板が掲げられていた。にゃにゃは猫を表し、七曲のように曲がりくねった路地だ。ここに赤や黄色など色が様々なら、大きさも姿もまちまちで、板をくりぬいたものや鉄製もあり、いたるところに猫サマがいて、何とも独特な雰囲気が漂い、脂汗がにじんだ。

「にゃにゃまがり」の路地を埋め尽くす猫たち

旧青梅街道沿いに点在する映画看板風に作られた絵やタイトルもユニーク。「映画の町」に加えて「猫の町」をアピール

映画「風と共に去りぬ」にあやかって「猫と共に去りぬ」と描いた看板も街角に下がる
路地を抜けて旧青梅街道に出た。いったん東に足を向け、戻って西を目指すことにした。道々に「怪猫二十面相」(「怪人二十面相」をもじった)、「第三の猫」(映画「第三の男」に倣った)といった看板やネコアート、オブジェがさまざまに設えてある。バス停にも猫サマがいらっしゃる。

旧青梅街道脇に立つ巨大な猫も〝歓迎デス〟と目を細める
レトロな昭和と猫に頬緩む
昭和レトロ感いっぱいなのが昭和幻燈館(住江町)だ。久保板観さんの作品をはじめ、主宰者の墨絵作家・有田ひろみさんとぬいぐるみ作家・有田ちゃぼさんのユニット「Q工房」の「青梅猫町商店街」、山本高樹さんの商店街のジオラマもあって存分に昭和を楽しめた。若い子もキャーキャーと言ってスマホを向けていた。歩けば歩くほどに猫に出くわし、つい、頬が緩む。

懐かしさと新鮮さが詰まった「昭和幻燈館」は昭和時代のびっくり箱

高度経済成長助走期の生活雑貨もある「昭和レトロ商品博物館」
その名も「昭和レトロ商品博物館」(住江町)に立ち寄った。元は家具店だった木造2階建て。2階の窓脇には黒澤明監督作品「七人の侍」(昭和29年=1954年公開)の映画看板が架かる。店内には昭和30~40年ごろのお菓子や薬などの商品パッケージを中心におもちゃ、ポスター、ドリンクなど生活雑貨を並べており、懐かしさで見とれてしまった。2階では小泉八雲の怪談「雪女」にまつわる資料を展示している。

祭の法被や仕事着などが所狭しと吊るしてある店の建物も目を引く

木造の箱型バス停。都営バスも止まる現役の停留所

アート感100%の公衆電話ボックス(住江町)。電話をかけないのにスマホを手に持ってボックスに入って気分を楽しむ人も

創業300年の「柳屋」(森下町)。創業時の商いはわからないとご主人。明治時代は木皮商で、昭和26年(1951)から茶業を営む

柳屋の店頭を飾る茶葉を入れる木製の棚

国登録有形文化財の津雲邸(住江町)。門も主屋も塀も文化財に指定されている。昭和9年(1934)京都の宮大工が中心になり建築した主屋は数寄屋風木造2階建ての入母屋造り。住んでいた津雲國利は昭和初期22年間、衆院議員を務めて、自邸を迎賓棟とした

国登録有形文化財 旧ほていや玩具店店舗(左=仲町)。外壁は銅板張りでいまも鈍い輝きを放つ。客間の2階バルコニーの張り出しは人造石洗い出し仕上げの円柱や手すりを設けて装飾している。昭和戦前の商業建築の好例だという

東京都指定有形民俗文化財 旧稲葉家住宅(森下町)の内部。江戸時代に青梅宿の町年寄を務めた家柄の豪商だった。間口5間半、奥行7間の土蔵造りの主屋表部分が店舗。江戸時代後期の建築
商売繁盛願う3体の猫神
江戸時代に青梅が生んだ絵師・小林天淵の手になる「雲竜図」を天井画にしていることで知られる住吉神社(住江町)。参道には猫の神様が3体あった。参道入り口左に昭和63年(1988)に地元商店街の人々が商売繁盛を願って奉納した「阿於芽猫祖神(あおめびょうそじん)」が涼やかにいた。招福殿と名付けられた祠に安置されている。阿於芽は青梅と青目を意味しているという。左手にマタタビの葉を持っている。神社拝殿昇り口の階段下左には「大黒天猫」、これに向き合って「恵比寿猫」が祭られている。

マタタビを持つ「阿於芽猫祖神」

大黒天猫

恵比寿猫
本殿脇にあった碑に目が行った。江戸中期の寛政から文化・文政時代、青梅の文芸最隆盛期のリーダだった根岸典則(つねのり)を称える碑だ。江戸の絵師・谷文晁の文人画に影響を受けて「青梅文晁」の異名がある小林天淵や江戸の著名な文学者・菊池五山らが中心になって建てたと説明板にあった。多摩の文化の源泉は、山間地にこそあるのだろう、と拝殿前から街を見下ろした。
暮らしと産業支えた猫にあやかる
なぜ、青梅の中心市街地に猫サマが徘徊するように出現するのだ?
青梅は江戸往還の青梅街道の宿場町であり、交易の地だった。戦前まで養蚕が盛んで織物の町でもあった。人の暮らしがあるところに虫や動物が寄生するのはいつの時代も同じ。鼠も多かった。どの家でも鼠除けに猫を飼い、かわいがった。さらに商人町の青梅では商売繁盛の縁起物として招き猫を店頭に置く店が多かった。「町の風景や昭和レトロの町並みとの相性の良さもあって」と青梅市観光協会のパンフレットにあった。だから「青梅は西ノ猫町」なんだと、さ。
町にあふれる猫や住吉神社に奉納された猫だけでは得心が行かず、歴史的な裏付けを求めて町を歩いた。耳寄りな話があった。

重層感がある瀑布山常保寺山門
薬袋降ろす鼠追う猫の悪説
青梅市立美術館(滝ノ上町)前にある臨済宗の常保寺(滝ノ上町)に猫が描かれた「涅槃図」があるという。釈迦の涅槃(死)図には像や虎、犬、鹿、猿、山羊、リス、亀、蛇、蟹、多くの鳥、虫など50種以上の生き物が描かれているのが一般的だ。どれも釈迦の死を嘆き悲しむ様子を描いたものだが、猫が描かれている涅槃図は少ない。奈良時代から現代に至る間、コリー犬など珍しい動物がいる涅槃図もあるというのに。
猫が涅槃図にないのは、こんな理由だった。
釈迦が臥せっているのを知った母摩耶夫人が天界から薬袋を降ろしたが、薬袋は沙羅双樹の枝に引っ掛かり、釈迦に届かなかった。これを見た鼠が木に登り、枝を噛み切り始めた。すかさず猫が鼠を追ったことで、鼠はその場から逃げて、薬袋は、ついに釈迦に届かず、死に至ったという。だから涅槃図に猫が描かれなかった。猫の悪説は江戸期を通じて一般に信じられおり、葬儀の場に猫を近寄らせない風習につながった。
涅槃会に参会する猫、各地に
江戸中期の浄土宗の学僧で全国を遊学した四休庵貞極上人は「猫が正念を乱すとの説は、人情をもってわけ知らぬ人が作り出した妄語が流布したものだ」と説く。釈迦の教えは、すべてのものを分け隔てなく救済することにあり、猫だけが涅槃会に参加できない訳がない、というのだ。
鎌倉時代(1185~1333年)~室町時代(1392~1573年)にかけて描かれた涅槃図に猫がいる。広島・浄土寺所有で文永11年(1274)作成図に猫がおり、室町時代初期に作成された京都三大涅槃図として知られる東福寺の涅槃図には魔除けの猫として描かれている。江戸期に入った元和10年(1624)作成の芝増上寺所有の涅槃図にも猫がいる。さらに京都・真如堂所有の涅槃図(宝永6年=1706年作成)には日本最多の動物127種が描かれた中に猫がいる。常保寺の涅槃図は、江戸中期(1700-1750年ごろ)の作品で、京都・東福寺の涅槃図を基にしたといわれる。
常保寺境内には招き猫の石像「猫地蔵」がある。穏やかな顔で目を大きく開けて左手を上げて招いている。元は青梅・裏宿町の無住寺院にあったが、昭和半ばに常保寺に移されたという。

養蚕が栄えた時代に地元の人々に大切にされた常保寺の「猫地蔵」
博識で豪放磊落な中原章を慕う
常保寺の創建は、応永元年(1394)に真言宗金剛寺(天ケ瀬町)2世によるものだが、1400年代ごろ(室町時代)に臨済宗に転宗した。江戸時代に寺を守った中原章師(?~寛政2年=1790年10月11日逝去。七十数歳だったか)は和学、雅楽、弓術、鷹狩りの故事、剣術に優れ、いつのころから常保寺に寄寓するようになり、学塾を開いて門下生を指導したという。漢学や和歌に長じた根岸典則、書家で著名な小峰峯真(ほうしん)、俳諧で活躍した師岡公貞らを輩出した。小峰峯真が記した中原章の人物像が墓表に刻まれている。これによると「先生(中原章)は少食にして多飲、もっぱら冷酒を愛好した。多摩川のほとりに14年ほど漂泊した後、庵を(青梅)市中に結び、慕って集まる人たちにいろんなことを講じた。晩年は髯をたくわえ、衣服なども意に介さず粗末な服装で通した。虱(シラミ)がたかっても、それをとることもなく、またつぶすでもなかった」と豪放磊落な暮らしぶりをつづる様子から町の人らと夜更けまで口角泡を飛ばして青梅文化の芽を育て合ったのだろう。
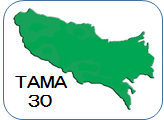 多摩めぐりブログ
多摩めぐりブログ