浅川に架かる橋に、その名前が人の名前に由来するという橋があります。 3月の声を聞き、春もそこまでという日に浅川に出かけました。八王子市平岡町から中野上町へと秋川街道(都道32号・八王子五日市線)が浅川を渡る橋・萩原橋がその橋です。
萩原橋は明治10年(1877)に南多摩郡中野村(現・八王子市中野上町)に器械製糸工場を建てた萩原彦七が私財を投じて架けました。
萩原彦七が工場を建てた中野村は湧水に恵まれ、桑畑が広がる地で、養蚕・撚糸が盛んに行われていました。糸を縒る動力となる水車も回り、良質な水は製糸業にとって最適なところでした。
工場ができた頃、浅川を渡るのには板の橋しかありませんでした。東京府は八王子・横浜方面への商用にも不便なので、板橋の補強を考えていました。しかし、将来の商工業の発展のためにも橋を架けたいという萩原彦七と地元の有志の強い願いが叶い、明治33年(1900)1月27日に木造の橋が架けられました。建設費は当時のお金で13,000円余りでした。建設費のほとんどを萩原彦七が負担しましたが、橋は私有すべきものではないとし、明治36年(1903)2月に東京府に寄付しました。
そして、橋の名前は功労者萩原彦七の名前に因んで萩原橋と名付けられました。
橋の南詰めの小さな公園に、建設功労者の名を刻んだ石碑が建っています。

萩原橋南詰めの公園に建つ石碑
当時木造だった橋は、昭和7年(1932)に鉄筋コンクリートの橋に架け替えられ、平成2年(1990)に補修工事が行われ現在の形となっています。
萩原橋の欄干には、浅川を背景に「蚕と桑の葉」、「糸車」等織物に関係した模様が刻まれています。

北詰めからみた現在の萩原橋


平岡町からみた萩原橋。浅川の上流には奥多摩の山々が望めます。
欄干に刻まれた模様






萩原彦七と製糸工場
萩原彦七は嘉永3年(1850)、相模国愛甲郡依知(えち)村(現神奈川県厚木市)の名主、座本左衛門の三男として生まれ、幼名を信吉といいました。12歳の時、雑貨店へ丁稚奉公に入った新吉は18歳頃には高座郡当麻村(現相模原市)の生糸商のもとで働くことになり、後に繋がる糸商人としての修行を積みました。そして、明治5年(1872)、八王子町小門(おかど)の生糸商人萩原彦七の番頭となった信吉は彦七の娘隈(くま)と結ばれ彦七を襲名することになりました。
八王子は江戸時代から織物の町として知られていました。明治の初め頃まで八王子に集められた生糸は遣水商人らによって盛んに輸出されていましたが、その後、粗製乱造により生糸の評判は海外で悪くなり、輸出は不振となりました。
明治政府は殖産興業の政策のもと質の良い生糸の輸出を奨励しました。生糸の生産も手繰り製糸から水車を使った器械製糸へと変わっていきました。
萩原彦七が中野村に製糸工場を建てたのはこのような時でした。
彦七は博覧会でも賞を受け、 製品は良質生糸として認められ、彦七の器械製糸の事業は大きく発展しました。明治26年(1893)には、養蚕伝習所を設け、生徒を養成する等、養蚕業の発展にも尽くしました。しかし、明治33年(1900)の生糸恐慌により価格が暴落し大きな打撃を受け、翌年明治34年(1901)には事業を手放すことになってしまいました。萩原製糸工場は信州の製糸業者片倉組が買収し、片倉製糸八王子工場と変わりました。
その後、彦七は再起を図ろうとしましたが叶わず、生まれ故郷に戻り昭和4年(1929)80歳で寂しくこの世を去りました。
萩原製糸工場の跡
萩原製糸工場は萩原橋から秋川街道を 五日市方面へ10分くらい歩いたところにありました。今は消防自動車のメーカー・日本機械工業という会社の工場となっています。
今も、日本機械工業の敷地の中には製糸工場時代の本社屋や工場などの古い建物が使われており、往時の繁栄の様子が伺えます。
秋川街道を挟んだ向かいの敷地内には製糸工場時代に蚕室だった建物が遺っており、最近まで社員寮として使われていました。

日本機械工業内の様子。右が製糸工場時代の旧本社屋・左はその工場

日本機械工業 第一南秋寮〜製糸工場時代の蚕室

表側から見た第一南秋寮、奥に見えるのは第二南秋寮
帰りは浅川の土手を歩きましたが、そこから街中に目をやると、かつては機屋さんであったと思われるノコギリ屋根の建物が残っていました。

中野上町のノコギリ屋根の建物
参考: 『八王子 中野町わが街』 清水正之
『多摩の百年 下 絹の道』 朝日新聞東京本社社会部
『多摩のあゆみ』第175号
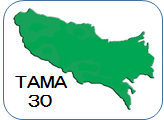 多摩めぐりブログ
多摩めぐりブログ