青梅線の白丸駅を出た下り電車は、長さ56.1mの白丸トンネルを抜けて再び1.27kmの氷川トンネルに入った。白丸駅から奥多摩駅まで2㎞区間の7割近くがトンネルだ。立川駅を起点にする青梅線37.2㎞、25駅目の終点、奥多摩駅は間もなくだ。令和2年(2020)1月20日、立川駅から始めたこのブログ「青梅線駅前の顔」シリーズは3年4ヶ月がかりで終幕を迎えた。

車窓や奥多摩駅周辺の山々を彩るフジだが……
深緑に映えるスプリンググリーン
奥多摩駅のホームに降り立つ。標高343mと刻んだ木製の標示板があった。立川駅から標高260mも登り続けてきた。特に青梅駅以西は蛇行する多摩川の左岸を這い、杉と桧などに覆われた山々が眼前に立ちはだかる。乗り慣れた路線であり、年間を通してことのほか新緑の時季が気に入っている。杉と桧の深緑が覆う斜面にスプリンググリーンと言われる若草色、若苗色、若葉色、萌黄色、柳葉色など明度が高い緑色系の絵の具を散りばめたようで山の斜面が躍動する。そんな車窓に点在するフジの花の淡い紫色の多さにいまさらながら気付いた。この現象は、山に手が入っていない証しだという。

氷川地区の中心地にある奥多摩駅
山小屋風の駅舎に先見性漂う
駅頭に立った。戦争一色だった昭和19年(1945)7月1日に開業した奥多摩駅舎は、いまも重量感がある。山小屋風であり、ヨーロッパの山上ホテルを思わせるデザインだ。暗かった時代にあって、この趣を際立たせた建築家の先見性に脱帽する。開業80周年が目前だ。
そういえば、平成16年(2004)まで3期奥多摩町長を務めた大舘誉さんは、平成15年に「町村長随想」(千代田区永田町、全国町村会発行)で、駅舎の着工当時の様子を語っていたのを思い出した。
少年ら電車に乗って行ったり来たり
大舘さんら子供の遊び場だった駅予定地の稲荷神社前広場に昭和17年(1942)突然、大勢の大人が集まり、大きな掛け声で作業が始まった。遊べなくなった不満と何ができるのかわからず頭が混乱した。その後、大人たちに聞いて鉄道の停車場の工事と知った。駅舎が完成して鉄道が運転を始めると、大舘さんら小学生は物珍しさとうれしさで毎日のように御嶽駅まで行ったり来たりして電車に乗って遊んでいた。
兵士送った場に焼け焦げた車両
太平洋戦争末期を迎える中で、駅舎は多くの若者を兵士として送り出す場となり、空襲を逃れる疎開者を迎える場になった。終戦の昭和20年には、駅は戦火に遭い、焼け焦げて赤さびた電車が係留されていたことを大舘さんは忘れることができない。

奥多摩駅の北側に隣接するようにある奥多摩工業氷川鉱山。元は石灰石を京浜方面へ青梅線で輸送していたが、トラック輸送に切り替えている。いまも北西へ直線で約10㎞地点の日原地区の石灰石採掘場から氷川鉱山へトロッコなどで地下輸送で運んでいる
会社設立から「神業」の開業
さらに大舘さんは、鉄道敷設の目的にも触れている。御嶽駅から氷川駅(現奥多摩駅)間の約10㎞の建設には町内日原地区に埋蔵する石灰石を掘り、運搬する目的の路線ではあったが、一般旅客や貨物輸送を行う地方鉄道として浅野セメント、日本鋼管、鶴見製鉄造船の共同出資で奥多摩電気鉄道株式会社によって敷設された。
この約10㎞区間は急峻な山岳地帯で、隧道14ヶ所、橋梁16ヶ所があり、5駅を設ける難工事だったが、会社設立から供用開始まで7年という短期間で建設された。当時、国民総動員下であり、重機もなく、資材も乏しい時代に「神業」としか思えない、と大舘さんは振り返っていた。
人を引き込む奥多摩の魅力
現在、「関東の駅百選」に選定されている奥多摩駅舎についても大舘さんは、印象深く綴っている。地元産材の大きな研き丸太を幾本も使った丸窓がある2階建ての贅沢な建物だ。いま、屋根は瓦葺きだが、当初は桧皮葺きだった。供用開始間もなく国鉄に買収され、いまJRに引き継がれている、と時代とともに歩んだ奥多摩駅舎を見てきた。
そんな奥多摩駅は、いまも変わらないどころか、登山者、レジャーの若者、外国人と、より一層利用者の幅が広がり、それぞれが奥多摩の水と風、緑が取り持つ縁で世界の交流の玄関口になっている。
電車とバス、100本以上発着
現在、奥多摩駅を発着する電車は平日60本、土曜・休日に72本。これに上りの回送車両が加わる。駅前からは奥多摩湖方面へ向かうバスの6路線をはじめ、日原鍾乳洞行きなど3ヶ所の乗り場から平日76本、土曜・休日に74本が発着している。奥多摩駅は、町民や観光客だけでなく山梨県小菅村や丹波山村の人々にとっても玄関口だ。

多摩産の杉や桧をふんだんに使っている奥多摩駅。登山者らが利用しやすいように更衣室やロッカー、靴の洗い場もある
改装した駅舎前にキッチンカー
高度成長期のころの奥多摩駅前といえば、ほとんどは登山者だったが、これに加えて今日では家族連れや若者、外国人が増えて駅前の様相はすっかり様変わりした印象が強い。中でもこの3年余りの新型コロナウィルスによるパンデミックで都県境にまたがる移動制限によって東京人は、奥多摩方面へ押しかけて道路が大渋滞した。

週末に奥多摩駅舎横で店を張るキッチンカーの「わさび食堂」に並ぶ人たち
いまも週末の午前中は、駅前の人だかりがすごい。キッチンカーが出店を張り、路地の飲食店では行列ができている。人出を当て込んだ居酒屋も昼から営業しており、店内の小さなカウンターはお客で満杯だ。駅ナカも変わった。ロッカーや更衣室、靴の洗い場を設け、2階では地ビールはじめ、コーヒーや軽食もいただけ、アウトドア用品なども販売している。

すっくと立つ奥氷川神社の「氷川三本スギ」
樹勢旺盛な東京最大の杉
駅前周辺の奥多摩らしい林層と水と風といった自然景観を求めて一刻歩いた。そそり立つ東京都指定天然記念物「氷川三本スギ」に吸い寄せられるように近づいた。三本スギは、奥氷川神社のそばにあり、ご神木として崇められてきた。都指定標識によると、大正13年(1924)の実測では目通り7.27m、高さ42.42mだった。現在発表されている目通りは9㎜太くなり、高さも49.3mに成長している。根元から3本に分岐しており、それぞれが直立して樹勢は旺盛のようだ。
スギは鎌倉時代に植えられたもののようで、都内最大の杉だという。地元の人がいうには多摩川対岸の愛宕山(507m)を氷川神のご神体としていた当時、ここを神庭として氷川神へ奉献するために植樹したものだ。落雷に遭っているというものの、青梅街道脇にありながら今日までよくぞ生き延びたものだと実感する。
境内に覆い被さる神域の愛宕山
奥氷川神社は、大宮の氷川神社、所沢の中氷川神社とともに「武蔵三氷川」と呼ばれる。奥氷川神社は、青梅中西部から奥多摩に至る一帯を氷川郷といっていた中世に社号を充てたものだろう。この界隈で最古の古社だ。本社は拝殿、幣殿と直線状にある。本殿の造りは元禄年間の造営を裏付ける間口3.14m、奥行き3.41mの明神造り。ここを拝所としたように主神がいる愛宕山は境内に覆い被さるように迫ってくる。駅前からも山が仁王立ちしているように見える。
山上にある愛宕神社の主神は火防の神「火産霊神(ひむすびのかみ)」で、山上から集落を見下ろせるという。社殿前にある長方形の自然石が、かつてのご神体だったという。

鮮やかな新緑が映える氷川渓谷。中央右の日原川から多摩川に水が流入している(昭和橋から)
光り輝く新緑に励まされて…
神域である愛宕山を目指した。奥多摩駅入口交差点から多摩川に架かる昭和橋を渡った右手、愛宕山園地で山道に入った。斜面を登るにつれて太い木の根がたこ足のように這い、急斜面では木製の階段が続く。息が切れる。先ほどまで下から這い上がってきていた女性の声が背後に感じるようになった。一呼吸入れる。5月の光を受けた木々の新葉が光り輝いている。薄緑、黄色っぽい緑など木によって緑系の色の濃淡が違い、きらびやかでさえある。
分岐点に到達した。直登すれば愛宕山、左へは海沢(うなざわ)、右へ行けば鋸山林道へ。2人組の女性は「いやだ、直登すれば188段の階段があるんだもの」と言って鋸山林道方向へ私より先に歩き出してしまった。
息も絶え絶えの中に熊出没情報
愛宕山山頂を目指す当方は、188段のコンクリート階段に内心、難色があるものの、足を前へ向けるしかない。山道の所々に女性像などのモニュメントはあるが、すでに見て楽しむゆとりはなかった。だが、杉の大木やアカマツなどの木々の存在感をいいことにして足を止めて眺めてきた。木に巻き付けてあったのは昨年8月7日の「ツキノワグマ目撃情報」だった。
188段の急階段に蹴倒された
園地入口から歩き始めて15分しかたっていない。目前に立ちはだかるのは188段の階段だ。階段は稜線まで垂直に延びているように見える。怖じ気づいた。でも、挑もう。後ろを振り向かない。手すりはあるが、足を踏み外したら、真っ逆さまに転げ落ちるに違いない。一歩、二歩と一段ずつ登る。中ほどの92段まで登って一休みした。

愛宕山の稜線まで続いているように見える188段の急階段
『帰り、ここは梯子段に見えて、足元が切れ落ちているんだよな』とつぶやいたことがきっかけで恐怖感が10倍に募った。山上にあるといわれる火防の神や五重の塔、平和の鐘などを見たいと思っていたことすら頭から消えていた。結局、折り返すことにした。188段の階段の途中で写真を撮っていなかったことに気付いたのは下山してからだった。
ワサビ三昧のおにぎり頬張る
ロング階段下のベンチで頬張ったワサビ三昧のいなり寿司とワサビの葉を巻いたおにぎりの何とうまかったことか。駅前に出ていたキッチンカー「わさび食堂」で買ったものだ。三々五々登ってくる人たちは、みな、健脚そうだった。若いころに次の電車待ちの間にひとっ走りしてこの山を登ったことが遠い昔のことになってしまった。

多摩川右岸のコースは優しい山道に変わった

根を露わにしたモミの木
渓谷美に心身が癒やされる
園地まで降りて多摩川右岸を遡る山道を選んだ。愛宕山の急登な登山道と違ってやや平坦だ。気温が高めのこの日、氷川渓谷の涼風が心地良かった。角張った露岩を巻く山道沿いにある木々は、初夏を待ち望んでいたというばかりに日差しは薄緑の葉を透かして降り注いでいた。馬頭観音があることから地元の人々はもちろん、いまの奥多摩湖周辺や日原などの村々からも行き交っていた道か、甲州へ抜ける道だったか。想像が膨らんだ。

織り成す木々の間に浮かぶ登計橋。下を流れる多摩川の水は新緑を映してエメラルドグリーンだった
吊り橋に秘めた惨状を刻む
数分でたどり着いたのは、多摩川に架かる吊り橋の登計橋(とけばし)だった。穏やかな流水と、葉を透かした陽射しの光景に、ここでも心身が休まった。
橋の手前に供養塔があった。安政6年(1859)7月の洪水で流失した橋を再興した氷川村の木村源兵衛さんに捧げた謝恩の碑だ。洪水は谷が怒り、橋を流し、道を塞いだ。そのことによって老人や幼子は泣き、飢えて、男、女は絶食に耐えたと悲惨な状況を碑は刻んでいる。洪水発生から47年後の明治39年4月に登計と長畑地区の人たちが建立した。惨事は長く伝えられていたことも碑は語っていた。

登計橋のたもとの岩上に立つ供養塔であり、謝恩の碑
登計橋の橋上から見る多摩川の上流は、蛇行していて谷の深さを物語る。下流に目を転じれば、北から流れ込む日原川と多摩川の合流点が一望できた。白っぽい石の川原では、老若男女それぞれが戯れている。穏やかな光景に気持ちが和む。
登計橋を渡り終えると、頭上に細い鉄骨がさらされていた。川原に荷を運んだ簡易式モノレールの線路だろう。

ツツジ(いずれも氷川渓谷で)

ツツジ

ミズキ

シャガ

ウツギ

サクラソウ
渓流挟んで手を振り合って
そうこうしているうちに再び吊り橋が見えてきた。日原川に架かる氷川小橋だ。多摩川との合流地だ。橋上で下流を見ると、日原川は多摩川へ直角に流入していた。

氷川小橋。橋の左下が日原川、橋の右上が多摩川
氷川小橋よりさらに日原川に沿って奥地へと進むと、狭かった空が徐々に広く感じるようになった。氷川国際ます釣場だ。水は、さらに澄んだように映る。対岸の川原では10人ほどの外国人の一団が遊歩道を歩く私に手を振ってくれた。振り返した手に応えて一団のメンバーは、今度は両手で気持ちを返してくれた。奥多摩の自然景観は“世界の人々を繋ぐ”。

新緑に包まれて渓谷風情がいっぱいの日原川
テラス席でクラフトビール
遊歩道の終点、日原川に架かる北氷川橋を渡って奥多摩駅に戻った。駅前の柳小路で木戸門に「青山居(せいざんきょ)麦酒醸造所」の木札を掲げる「ビア・カフェ・バテレ」(土、日曜11時~19時半営業)で喉の渇きを癒やした。ここは古民家をリノベーションしたマイクロブルワリーだ。テラス席を囲む若葉のスクリーンと日原川から上がる水音、野鳥の声も一品になり、テーブルにビールグラスを並べた。このブログの「青梅線駅前の顔」シリーズを打ち上げるのに最良の舞台になった。

清々しい風が通るビア・カフェ・バテレのテラス席

ソーセージの盛り合わせと鶏ハムわさびドレッシングをいただいた。左のビールが黒糖やチョコレートを思わせる香りがほんのりある「ウルムス」、右は蜜感があり、フルーツ味の柔らかさを楽しめた「クロウェア」
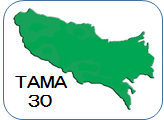 多摩めぐりブログ
多摩めぐりブログ