
清水川と矢川が谷保分水に合流する「矢川おんだし」
刈り取った稲を干す光景ものどかだった
小春日和だった10月20日、6回目の多摩めぐりで、立川崖線と青柳崖線をゆっくりと歩いた。段丘崖(ハケ)から染み出る湧水の清水さを強く感じた。歩きながら地形の微妙な変化を逃さない眼を持ち続けることも意識した。武蔵野台地を形成している高い位置にあるのが武蔵野面で、順次下がってきて立川面、一番低い多摩川に近いあたりが沖積低地だ。立川面の下り斜面が立川崖線、ここから枝分かれしているのが青柳崖線だ。崖線の作り手は「東京の母なる川」多摩川だ。太古の時代、関東平野は海水に浸かっていた。海が次第に後退し、6万年以上前に多摩は陸地化し、西の山間から流入した川水は、今日にいう多摩川となり、台地を我が物顔で蛇行して武蔵野台地に砂礫が堆積した。3万年~5千年前には気候の寒冷化による海面低下となり、多摩川の流れは急速になり、台地をえぐった。北に国分寺崖線、その南にある立川崖線、青柳崖線は、いずれも東西に連なる多摩川の爪痕だ。この一帯はいま、動植物が棲むグリーンベルトであり、湧水べりは近隣の人々の憩いの場になっている。
目次
1.立川崖線
海の底だった武蔵野台地
この日の集合地は、立川市羽衣町1丁目、JR南武線西国立駅前。ここは武蔵野面よりも一段低い立川段丘で、東の調布市までが平たんな立川面であることを知った一行23人は、つい足元に目を向けた。心躍るワクワク感の表れか。
スタート後、南へ緩やかに下ること数分。立川面よりも一段低い青柳面との境になる立川崖線に近づいた。立川崖線は、西の青梅付近から東は狛江市和泉町まで多摩川左岸に沿って約40㎞延びている。
立川崖線の出現は、3万年~2万年前に遡るという。関東平野が海の底だったころ、河川から流入した砂礫が海底で固結して上総礫層となり、幾度か、氷期と間氷期を繰り返す一方、陸化と海化も繰り返したと考えられている。造山運動も加わり、いまの多摩川は、狭山丘陵南面から徐々に南下の流路をたどった。これらの過程で表層だった下末吉面が流されたところが武蔵野面になり、さらに立川面が出現し、その南端が削り取られて立川崖線として残ったといわれる。
多摩地域では、崖線のことを「ハケ」という。河岸段丘の斜面(段丘崖)が長く延びている様子を表す言葉で、坂道を指す言葉でもある。武蔵野台地は、表層に黒土層があり、その下に関東ローム層、砂礫層と深まり、基盤になっている上総層群で地層を構成している。上総層群は、浸透した水が飽和状態にあることから、湧水は砂礫層から染み出し、ハケ下を潤す。この日のコースでそのポイントがいくつもありそうだ。
2.矢川弁財天
立川崖線を背に水映える青柳面
立川崖線を下る「みのわ通り」に立ったら、池を取り込んだ矢川弁財天が足下にひょっこり現れた。その境内はハケ下から湧水を取り入れた「龍神の池」と本殿の配置の良さか、立川崖線と青柳面を取り込んだ箱庭のようだった。白蛇の狛犬にも一行の目が集まった。狛蛇は、細やかに施された鱗といい、ふくよかな太り具合が見る人を安堵させる。

蛇狛をまつる矢川弁財天
3.矢川緑地
水源一帯に自生する豊かな生き物たち
矢川弁財天から歩くこと2~3分の東側に矢川緑地があった。広さ2.1haと小規模だが、入り口の様相は、動植物が多く棲んでいそうな深山の趣だ。ここは湧水源であり、水量豊かな矢川は幅2mほどか。流水沿いの遊歩道は、すでに雑木林の中だ。ケヤキ、コナラ、クヌギ、ハンノキ、スダジイ、シラカシ、ムクノキなどが自生する光景は、里山の風情だ。炭や薪が欠かせなかった当時の生活と、開墾前の武蔵野の雑木林の光景を想像した。
武蔵野台地の武蔵野面と立川面は、水がなく、先人は開墾に苦労した。だが、ハケ下は水が豊富だ。中でも矢川緑地には湿地があり、水辺特有のアキノウナギツカミ、ミゾソバが楚々と咲いていた。水路には準絶滅危惧種に指定されているナガエミクリ、ミクリ、ミゾホウヅキも自生している。その脇の水面をカモの番が互いにゆっくり動き、餌をついばんでいた。野鳥のさえずりのシャワーの中、木道を歩いた。

秋の花が連なり、矢川緑地の木道歩きも楽しんだ

アキノウナギツカミ
4.矢川
水多く、矢の如し速かった流れ
矢川緑地一帯を水源とした矢川は、流水が矢のように速いことを表した名だそうだ。緑地を流れ出た矢川は南の甲州街道をくぐり、青柳崖線のハケ下にある「矢川おんだし」で府中用水の支流である谷保分水に合流して最終的に多摩川に注ぐ。

水草の色が際立つ矢川
矢川の澄んだ流水とともにしばらく国立市青柳の住宅地を縫うように歩いた。近隣住民が保全しているのだろう、川には空き缶やビニール袋などのゴミがない。ここでもナガエミクリ、ホザキノフサモ、アイノコイトモなどの水草が秋の陽光に映えていた。ホタルが飛び交っていた元の環境を取り戻そうと活動している人々もいる。昭和の初めまでワサビ田もあった。生糸の生産に欠かせない動力だった水車も活躍していたという。それほど水が澄み、水量が多かった。
5.青柳崖線
船底の船首部分にあたる緑の島
甲州街道を横断すると、ほどなくして再び緩い下り坂に差し掛かった。立川面から青柳崖線に差し掛かったのだ。この坂は短かった。
多摩川に最も近い青柳崖線は、東端が国立市谷保の谷保天満宮だというから、ここ青柳からは近い。西端は立川市錦町の柴崎体育館裏手で立川崖線につながる。その距離は3.8㎞だという。

黄金色に輝く田んぼの背景に浮き立つ青柳崖線
上空から見る青柳面は船底形で、青柳あたりは船首部分にあたる。周囲は、田畑が少なくなって住宅など建物が目立つ。開発の手から逃れた青柳崖線は、緑の細島か。落葉樹のコナラ、エノキなどの高木相があり、ヤブツバキ、アズマネザサ、アオキといった低木相も濃い。
6.ママ下湧水
清らかな水と木々と黄金色の稲穂
青柳崖線のハケ下からこんこんと湧く水源の代表格「ママ下湧水」。多摩川の沖積低地にある国立市矢川3丁目。ここも矢川緑地の湧水とともに「東京都名湧水57選」に選定されている。水は夏場も枯れない。絶滅危惧種に指定されているホトケドジョウが生息しているほか、小型の水生生物が見られる。カモの親子連れだろうか、3羽が我ら一行に場所を譲るように田んぼのあぜ道に身を寄せた。
湧水は、年間を通して17度と知った一行のメンバーは、湧水に手を入れた。「あ~、ひんやりして気持ちいいっ!」と、秋にしては高めの気温の中を歩いて汗ばんだ体に涼を得た。
湧水の水源前の田んぼでは収穫目前の稲穂がたわわに実を下げ、色づいていた。湧水は清水川となって田んぼを囲み約20m区間、矢川と並列してともに府中用水の支流である谷保分水に流れ込んでいた。この合流地を「矢川おんだし」といわれている。
崖線の緑と水辺空間の穏やかな光景に心が休まり、別の田んぼではすでに刈り終えた稲を丸太で組んだ棚に下げて干していた。懐かしい農村風景に色濃い秋を感じた。

「ママ下湧水」に見とれる参加者たち
7.青柳稲荷神社
多摩川氾濫で移住地の平安を願う
西に向かって歩く。青柳面は平たんだった。左側は多摩川。ハケの斜面に木々が覆い茂り、絶好のウォーキングコースだ。サイクリストも行き交う。
ほどなくしてあったのは青柳稲荷神社だ。360年ほど前に多摩川が大洪水に見舞われた。多摩川の対岸にあたる現在の多摩市一宮や関戸の住民とともに暮らしていた青柳の人々は、被災した。その後、移り住んだのがいまの国立市青柳。同じころ、現在の日野市石田からも移住した。これらの集落の人々が安寧を願って青柳稲荷神社を祀ったという。
8.府中用水取水樋門
300年以上、多摩川中流域を潤す
青柳崖線をさらに西へ進む。南側が開けて多摩川が一望できた地点が府中用水取水樋門の上だ。江戸時代中期の元禄6年(1693)、多摩川中流域の国立市、府中市の多摩川に近い沖積地の灌漑用水として多摩川から水を取り入れた。今見られる取水樋門は、大正期に造られたもので4口のうち3口が現役。現在の水の取り入れ口は、日野橋の下流約80m。樋門を通過した水は、青柳崖線のハケ下を縫うように東へ流れて、調布市国領町で多摩川に注いでいる。農繁期を中心に稼働している。
堰堤に立ったメンバーは「来季の農繁期に再度、ここに来て樋門に吸い込まれていく水の勢いを見たい。ハケ下の田んぼや畑を耕作する人々の躍動感を感じたい」と樋門を見続けていた。
府中用水は、日本の農業を支えてきた代表的な用水として農林水産省が「疎水百選」に選定した。東京都で唯一選ばれた。

300年以上、田畑を潤した府中用水の取水樋門
9.根川緑道
小川風情の水辺に誘われる公園
青柳崖線の西端に近づいた。国立市の出口であり、立川市の入口でもある地点に根川が横たわっていた。ここに架かるのは「根川貝殻橋」。鉄骨造りの板敷きの橋だ。根川緑道の東端でもある。江戸時代前期の慶安年間(1648-51)から貞享元年(1684)まであった多摩川の「万願寺の渡し」を使う人々が、青柳崖線の上をたどる甲州街道を下って、さらにハケを降りて渡し舟に乗ったという。
根川は、かつて立川崖線と青柳崖線のハケ下の湧水が集まったのどかな川だった。明治26年(2893)から41年にかけて玉川上水と残堀川が改修された際に残堀川を根川に合流させた。その後も根川は、残堀川とともに何度も氾濫した。

解放感あふれる根川緑道を西へ進む
残堀川と切り離した根川には今、高度処理水を1日約2700t放水している。人工の水辺公園なのだ。並木の桜は紅葉目前で、葉に目をやりながら、堤防の法面の緩やかさに誘われて水辺を歩きたくなる衝動を抑えた。遊歩道沿いには歌碑がいくつも立つ。野鳥や魚が手に取れそうなほど近い。
柴崎体育館裏手の濃い緑は、立川崖線を覆う木々が重なる。この辺りで青柳崖線は立川崖線につながっている。根川の水の噴き出し口を過ぎると、立川崖線のハケ下に着き、残堀川の遊歩道に入る。

根川緑道の西端で参加者勢ぞろい
10.残堀川
氾濫繰り返して付け替え工事
残堀川は、西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎の狭山池が水源。武蔵村山市、昭島市を南下して立川市に入る約14.5㎞の1級河川だ。根川の水の噴き出し口付近から100mほど下流で多摩川に入る。
瑞穂町では残堀川を「蛇堀川(じゃぼりがわ)」というほど大雨の後、あふれ出た水は、蛇が狂ったように暴れることからそう呼ぶという。これまで見てきた矢川や清水川、谷保分水の小川の風情とは違う。

絶壁の立川崖線から下がる木の枝
深く削り込まれた残堀川
川幅は見た目で8mほど、川底は遊歩道から5mも下だ。めまいするほど深い。その深さをさらに強くするのは、左岸の立川崖線の絶壁だ。高低差は15mもあり、崖線随一の高さだ。遠い昔、荒れ狂う残堀川の水が崖線を削りに削った証だろうか。
それだけに残堀川は、幾度も手を加えられた。玉川上水の通水(承応3年=1654)前の残堀川は、立川断層の崖下を狭山池から南東へほぼ直線的に流れて、国立市谷保で多摩川に流入していたという。玉川上水の建設によって、立川市上砂町で残堀川を横断するため、残堀川を玉川上水につないだ。しかし、明治時代、織物産業が興隆して箱根ヶ崎や武蔵村山の染色工場の廃水などで上水が汚染されたため、明治半ばに2本を分離させ、残堀川を玉川上水の下に通して交差させる改修工事をした。ところが、これがもとで長雨や豪雨の時に残堀川は、たびたび氾濫した。その影響は根川にも及んだ。このため、残堀川と玉川上水の交差地点を再び改修した。昭和38年のことだ。残堀川を上に、玉川上水を下に入れ替えて、玉川上水の通水をサイフォン式に改善した。昭和47年の残堀川と根川を切り離す工事で落ち着いたのが今の姿だ。
 ガイド:山下さん
ガイド:山下さん
爽やかな秋空のもと、清らかな湧き水や矢川の水音に耳をすませば、小鳥のさえずり。日ごろ、忘れかけていた自然に接する喜びを感じさせてもらえました。学園都市の国立と別の世界。太古から人々が水とともに過ごした地でした。これに対して残堀川は、人々との戦いに似た歴史がありました。そして、普済寺は立川の歩みを現在まで伝えてきました。大都市立川の違った側面を知る機会となり、やはり、歴史から学び、発見する楽しさも感じた一日でありました。
11.普済寺
展望開ける境内に国宝「六面石幢」
残堀川に架かる中央線鉄橋の手前で急坂を登った。高低差は10m以上だろう。この坂こそ、立川崖線を登り、崖線上に立つ道だ。着いた普済寺境内で目に飛び込んできたのは、北西に秩父・奥多摩連山、南に丹沢山系だ。
この日のもう一つのお目当ては、国宝「六面石幢(せきとう)」を見ることだ。高さ2.45m。秩父の緑泥片岩で作られた六角柱の供養塔で、境内や墓地の清浄を願ったものだ。小堂に守られた石幢は、天頂の笠石の上に凝灰岩でできた宝珠を設え、その下の六面それぞれに阿吽の金剛と持国天、多聞天、広目天、増長天を緑泥岩の板石に彫って組み合わせている。いずれも動勢豊かだ。北朝時代の延文6年(1361)の調整であり、元は、いまの位置より西側の墓地に露天設置していたというから歴史感がある。
普済寺の開山は北朝時代だ。文和2年(1353)、立川一帯を領有していた立川宗恒が鎌倉建長寺から高僧物外可什(もつがいかじゅう)禅師を招いたことに始まる。立川氏は、武蔵七党の一つ、日奉氏の出自だという。16世紀に一旦、勢力が弱まった立川氏は高幡城主・平山氏の帰依を受けて小田原北条氏の幕下となり、普済寺は再び立川氏の保護を受けた。
崖線は戦国時代も有効だった。ハケを防壁として館を構え、一帯を所領して支配していたことを示すのは境内に残る土塁だ。だが、豊臣軍の東征で小田原北条氏とともに立川氏は敗れ、普済寺は堂宇や寺宝を焼失した。一族は、水戸徳川家に抱えられ、常陸太田の佐竹氏の家臣になった。
復興したのは江戸時代に入ってから。「江戸名所図会」に描かれ、明治時代初めには立川の文化・教育の拠点になった。「立川教育文化発祥乃地」の碑が境内に立つ。
平成7年の放火事件後、10年がかりで再建された普済寺は、真新しい景観を漂わせる。本堂の青海波紋様、庭の敷石、太鼓橋などを配したせせらぎに清浄さを感じた。玉川上水から引き込んでいる柴崎分水が山内に流れ込んでいることも当時の支配力を物語る。
弓場重典(ゆば じゅうてん)住職は、江戸市中の繁栄時代には、この周辺は木材不足で寺の修理もままならなかったことや、この寺で皇族が静養した時代があったことなど、寺にまつわる出来事を話した後、自慢の庭を案内してくださった。

庭から普済寺本堂も見学した一行
多摩川が武蔵野台地に刻んだ長い崖、崖線。地元の人々は、自分たちが住んでいる地域の崖を「ハケ」と呼んできました。湧水が得られるハケ下は、人々はもちろんのこと、動植物にとっても生きるために欠かすことのできない場所です。「ハケ」の言葉は、次第に忘れつつあるといわれています。豊かさと潜在力をあわせもつ自然を理解するためにも生き続けてほしい言葉ですね。
 ガイド:相山さん
ガイド:相山さん
【集合:JR南武線西国立駅 午前9時/解散:普済寺 午後3時30分】
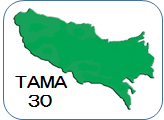 多摩めぐりの会
多摩めぐりの会