
ガイド:味藤 圭司さん
JR青梅線東青梅駅北口(集合)⇒ バス停・成木1丁目自治会館前 → 安楽寺 → 富岡2丁目児童遊園【昼食】→ 常福寺 → 岩蔵温泉 → 上の台(うえんでい)→ 御嶽神社 → 石倉(せきそう)院 → 大岩(立川断層)→ バス停・岩蔵温泉 ⇒ JR青梅線東青梅駅北口(解散)
東京の最高気温が25度を超えた3月23日、青梅線東青梅駅から北へバスに乗ること20分ほど。東京・埼玉の都県境である青梅市成木の緩やかな丘陵はピンクの桃の花で彩られていた。冬枯れの裸木が林立する中にあって、ピンクの丘は、まさに“彩の島”だった。この日は令和7年初めて開催した多摩めぐりで参加者20人を味藤圭司さんがエスコートした。一行が歩いた先々は奥多摩方面から迫り出した山域の東端域で丘陵が幾重も覆い、山里に長く伝わる伝統行事が生き延びていた。寺院では日本を揺るがした人々がここでも存在感を知らしめていた。杉や石灰、泥炭といった地域特産の産業の形跡を知り、露岩の大岩も地元の人々が崇め続けている。そんな暮らしぶりを思い描いた。

ある時、安楽寺の色鮮やかな桃畑の写真を見てその景観に圧倒されました。こんなに素晴らしい風景が多摩にあったのだ!と。花の時季の現地の状況を見ていないにもかかわらず、花の盛りにぜひ訪れてみたいと早速、桃の花が咲く時季に多摩めぐりのスケジュールに組み入れました。
周辺情報を集め始めると、安楽寺は名刹といわれるように由緒と歴史がありました。さらに足を延ばせば、東京都に数少ない温泉である岩蔵温泉を訪ねることもできることを知り、今回の多摩めぐりのコンテンツを膨らませました。
現地を歩くと、吊り下げられた草鞋(わらじ)が目に入って、これがフセギ行事の草鞋で地域の6ヶ所にあることがわかりました。この6ヶ所の草鞋のクエストも行程に組み込むことで、全体プランが出来上がりました。中身の濃いコースに仕上がったと思っています。
当日の天気は晴天。桃の花は8分咲きといったところで、思い描いていた通りの多摩めぐりを参加された皆さんとともに楽しめたのではないかと思っています。
平安時代製作の金剛力士像
都道193号を走ったバスを降りて、目指す安楽寺は百数十メートル北側に入ったところだった。沿道の畑にはナノハナやウメが咲き誇っていた。正面にどっしりと構える安楽寺の仁王門(3間×2間=5.4×3.6m)が横たわる。この奥にある軍荼利(ぐんだり)明王堂の入口だ。背後を覆う丘陵斜面の木々に浮かび上がり、厳かさを醸し出している。

仁王門左手に立つ金剛力士像は高さ約210㎝と背丈がある。カツラの一木造りで、全身がすっきりしている。中世以降の仁王像の筋骨隆々の姿とは違う。中世以前の平安時代の古い像とみられている。右側の伝金剛力士像もカツラの一木造りで像の高さは約190㎝。怒髪天を突き、目を見開き、口元から歯がのぞく。胸の前に右手を置き、親指と人差し指を立てている。左手は肘を折って腰のあたりに構える。全体的に素朴だが、力強さを際立たせている。2体は東京都有形文化財。


小顔で深い彫りの明王像
仁王門の奥に立つ軍荼利明王堂は5間4尺×5間2尺(10.2×9.6m)。歴史を感じさせているのは堂の脇に立つ銀杏の大木だ。枝の下方に垂れ下がる乳根の大きいこと。明王堂の別当が安楽寺。
本尊の軍荼利明王は八臂の形で高さが約3m。体躯は平板で衣の襞の線が浅いという。頭部に奥行きがあり、体に比べて顔は小さいが、彫りが深いともいう。眉や目、鼻が大きい分、力強さが漂うそうだ。行基の作と伝わる。江戸時代に江戸で行われた出開帳に出向いた時に光背を補ったらしい。今日の軍荼利明王像は秘仏としており、毎年8月14日に開帳している。

華やぐ桃の花“彩の島”
軍荼利明王堂から安楽寺へ向かう途中、右手の南斜面がピンク色で染まっていた。モモの花だ。全開の花びらに混じって赤く染まった蕾も重なっている。150本を超えるハナモモが整然と植栽されていた。足下に広がる枯れ草の軟らかさが伝わって気分が軽い。桃源郷を全身で味わった気分だ。
30~40年ほど前、山梨県の業者が安楽寺から借地した30aにハナモモを栽培したのが始まりという。業者が撤退した後に残されたのが桃源郷だ。近所の人々が、この日の暖かさに誘われて幾組も散歩にやってきていた。知る人ぞ知るポイントで、多摩めぐりの参加者も「いや~見事だ。ここに座って過ごした~い」という思いを強くした人たちが多かった。

威厳を放つ白と黒の塀
参加者の気持ちを引き締めたのは、威厳を放つ安楽寺の白壁と黒くなった板塀だ。本堂前の塀際の大杉も異彩を放つ。見上げる目線も高い。幹回り6.5m、高さは37m。一帯はスギの産地で、近間で知られた埼玉・西川材に隣接している。見上げる境内のスギの中腹にコナラが寄生していた(現在、枯れてしまった)ことから「やどり木の大杉」(東京都天然記念物)と言われている。塀を背にして南を見ると、山間地に開けた集落が一望できる高台だった。

長屋門と表門を構えた安楽寺は、真言宗系単立寺院で、正式には成木山愛染院安楽寺という。縁起によると、奈良時代の和銅年間(708~714)に僧行基が布教教化の折に山上のクスノキの巨木が鳴動して光を放った。その光の中に軍荼利の姿を見たことからクスノキを切って1丈2尺(約3.6m)の軍荼利明王を彫って堂に安置したのが始まりだ。クスノキが鳴ったから鳴り木とし、山号を成木山とした。所在地も青梅市成木。

頼朝、尊氏らも寄進した
安楽寺のゆかりの人に源頼朝がいる。頼朝は家臣の畠山重忠に命じて念持仏愛染明王を納めて愛染院を建立した。暦応年間(1338~41)には足利尊氏も大泉坊、吉祥坊、多門坊など6僧坊を建てさせて、近隣の武士、僧侶に大般若経600巻(青梅市有形文化財)の写経奉納を命じた。その後、奉経は文明9年(1477)までの115年間続けられた。
堂宇も什宝も焼けた歴史はあるが、永禄年間(1558~69)には鎌倉の僧賢能が再興して中興開山一世となった。天正19年(1591)には徳川氏から寺領7石の朱印状が寄せられ、江戸時代に入って京都・仁和寺の直末として29ヶ寺をまとめる檀林になった。29の末寺は青梅市内に8寺あったが、現存するのは安楽寺のほか3寺(常福院=成木7丁目、延命寺=同、福昌寺=小曽木3丁目)。
都内最古の書院風建築
元禄6年(1693)に寛晃が再建した本堂(東京都有形文化財)は、昭和52年(1977)から59年まで2期にわたり、法堂と仁王門を併せて修理した。山中に泰然と立つ本堂の風情と境内の静寂さに心身が洗われるようだった。
本堂は桁行12間(24.5m)、梁間7間(14.48m)で寄棟造りの大屋根が載っていた。8間取りの方丈型本堂で書院風建築だ。都内の書院風建築で最も古く、元禄以降、大きく改築されていない古い様式を残している。茅葺屋根だったのを昭和の修理の際に茅葺型銅板葺に改修した。

鉄砲鋳造で消えた梵鐘
表門の西隣にある鐘楼は時代を映していた。寺には天正16年(1588)に北条氏直から送られてきた「鐘借用状」(青梅市有形文化財)がある。豊臣秀吉の関東攻めに備えるために鉄砲鋳造に充てる梵鐘を借用したいという朱印の文書だ。これによると、世が落ち着いたら、鐘は鋳造し直して返すとある。だが、北条氏は滅亡して、以来、鐘は還ることがなかった。慶安3年(1650)には僧賢重が鐘を鋳造したが、その後、鐘損。再び鋳造した享保16年(1731)の鐘が今も現役だ。

さらに鐘楼の西隣にあるのが宝塔といわれる宝篋(ほうきょ)印塔。高さ2丈5尺(約8.3m)、縦横2間半(約3.8m)の塔の中に高さ1尺6寸(約48.3㎝)ある木造座像の愛染明王を安置している。座像は弘法大師の作といわれ、源頼朝が納めたと伝わる。両脇では約7寸(約21.2㎝)の多聞天と吉祥天が脇侍を務めている。
城壁を固めた成木石灰
ガイドの味藤さんは、安楽寺の前で塀に使われている白壁を指さして当地の成木で採掘していた石灰石について話した。石灰(いしばい)と呼ばれる石灰石の産出量が多かったことは戦国時代に江戸まで響いていたという。江戸幕府が開かれる前の天正18年(1590)から成木で石灰焼きが行われており、八王子城などの城壁にも使われていた。このことを知った徳川家康は慶長11年(1607)、江戸城の大改築の折に一層、堅固な城壁にするために土壁を改め、漆喰(しっくい)を使った漆喰壁を取り入れた。江戸周辺で大量の石灰石を採掘していた成木に目を付けた。八王子代官だった大久保長安に命が下って上成木村(現在の成木6丁目)と北小曽木村(成木8丁目)の窯主に用立てさせて「御用石灰」として輸送した。両村には木材の燃料資源が豊富で、漆喰を生成するのに欠かせない水も成木川と北小曽木川があり、生産の資源には事欠かない立地にあった。

石灰の輸送用に拓いた街道
輸送ルートを整備して拓いたのが甲州裏街道といわれた青梅街道だ。生産された成木石灰は一旦、集積場(現在の成木4丁目にある成木市民センター付近)に集め、その後、石灰を富岡丘陵や笹仁田峠を越えて箱根ヶ崎(瑞穂町)へ馬車で運んだものか。箱根ヶ崎までのルートが当初の青梅街道(今は岩蔵街道)で、これより東方へは今の青梅街道と同じルートを上った。後に入間川や新河岸川(いずれも埼玉県)の舟運に取って代わられていった。上成木や北小曽木の産出も減り続け、大正8年(1919)、9年には成木石灰は生産を終えた。
Uターンで再出発したTOMIOKA
安楽寺の旧参道を下り終えた地点に高さ2m超もあろうかという大きな石碑があった。昭和33年(1958)に地元出身の富岡正重が寄進した。富岡は大正13年(1924)に高級レンズの設計・製造する「富岡光学」を大森区雪ヶ谷(大田区雪谷)を創業して潜水艦の潜望鏡や零戦の照準器などの光学機器を陸軍や海軍に納品して事業を拡大した。一方で富岡は空襲を逃れて青梅の霞村新町(現在の青梅市新町)に疎開して生産を続けた。戦後、再出発の地は、故郷の同市小曽木だった。「富岡のレンズ」はカメラ愛好者の羨望の的で、カール・ツァイス(ドイツ)と提携するなどして世界的なブランドにのし上がった。だが、昭和48年(1973)からのオイルショックには勝てず、親会社だったヤシカが京セラグループに吸収されて以来、いまも変わらず京セラ事業所の一つとして同市小曽木で操業している。

落ち延びた姫の尼寺
多摩めぐりの一行は、長くながく感じられた日影林通りを南下した。途中の児童遊園で昼食を採って一休みを兼ねた。西側のゴルフ場を避けるように曲がる道、そして峠。茶畑の脇も歩いた。さらに坂下の集落から藪の細道を抜けた。目指していたのは曹洞宗萬貴山常福寺(青梅市富岡)だ。門前に細い川が流れ、本堂裏に小高い山が迫る。その中腹に鐘楼が立つ。山里の集落に鐘の音が響き渡るような小高い場所だ。

常福寺は500年ほど前(大永7=1527年)、萬貴姫(まきひめ)が開基したと伝わり、武蔵国高麗郡下直竹村(現在の飯能市)の長光寺六世三翁守島が開山した。裏山に卵塔を建てた「比丘尼塚(びくにづか)」がある。

青梅市に伝わる「比丘尼塚」の昔話がある。鎌倉時代末ごろ、万貴姫(まきひめ)が侍女5人とともにここに落ち延びてきた。姫は草庵を作り、尼となって世を忍んで暮らしていた。戦や飢饉が続く中、人々の暮らしは悲惨を窮めていた。托鉢で得た米や銭を飢えに苦しむ人々に分け与えた。これを物相飯(もっそうめし)といい、周辺の地名も木狐入(もっそういり)という。やがて姫が亡くなると、侍女たちは山に姫を埋葬し、托鉢の帰り道に塩船観音(青梅市塩船)境内の土を鉢に一杯ずつ入れて持ち帰り、姫の墓に盛った。墓は次第に塚となり、比丘尼塚と呼ばれるようになった。この墓を小曽木村の人が明治期に掘ったところ、金銀の小刀、鼈甲(べっこう)の櫛、笄(こうがい)、瓔珞(ようらく)、首飾りなどが出たという。
疫病や悪霊払う“草鞋ゲート”
次に訪ねたのは岩蔵温泉(小曽木5丁目)だ。北の飯能と南の青梅を結ぶ飯能街道の中間地にあたる往時の宿場であり、高度経済成長期に連夜、飲めや歌えの宴が続いた宿が立ち並んでいた温泉町だ。
富岡地区と岩蔵地区の村境になる黒沢川に架かる湯場橋の右岸詰めで括り付けた竹の上方に草鞋が吊るしてあった。これが「フセギの草鞋」だ。疫病や悪霊が村に入らないように、あるいは村の中にある災厄を村の外へ追い出すことを願って注連縄(しめなわ)や大きい草鞋を吊るして災厄除けをしている。

岩蔵地区では毎年7月下旬の日曜日に愛宕神社の例祭に合わせて、「お精進」と呼ばれる草鞋作りが行われている。長さ40㎝ほどの草鞋を編んで、隣接する4地区6ヶ所の村境に吊るしている。草鞋の中ほどにそれぞれ1つから6つの穴を開けて6足を編んでいる。吊るされた草鞋は、どれも風雨に打たれながらも編目やワラの腰が残るものなどしっかりと形が整っていた。なぜ、草鞋か? 村には恐ろしい巨人がいることを示して威嚇しているといわれる。素朴ながら艱難辛苦を乗り越えてきた先人の知恵を表した民俗風習の尊さを印象付けている。令和元年(2019)に東京都無形民俗文化財(風俗習慣)になった。

4地区の村境6ヶ所に吊るす
フセギの草鞋を見るために湯場橋のほか、他の全5ヶ所を訪ねた。①岩蔵と小布市(こぶいち)の境の消防団詰所脇。昨年以前の草鞋も吊るしてあった②岩蔵住居跡の南200mほどの上の台(うえんでい)③岩蔵と古武士(こむし)の境、小曽木街道沿いの民家脇④岩蔵の大岩⑤岩蔵と富岡の境で小曽木街道に架かる境沢橋。
地域の境界に草鞋を吊るしているのは都内では岩蔵地区と東方の青梅市谷野地区。清瀬市下宿では「ふせぎ」といってワラで全長20mほどの大蛇を2本の木に掛けている。「フセギ行事」に似た「道切り」は秩父など埼玉県西部域で見られる。
懐かしむ都内唯一の温泉郷
いま岩蔵温泉街では「儘多屋(ままだや)」が営業を続けるのみで、かつての賑わいはなかった。岩蔵温泉の泉質はアルカリ性単純硫黄鉱泉で肌が滑らかになり、美肌効果が期待できるという。日本武尊が湧き出る湯で潔斎して戦塵を払った。その折に岩蔵に武具を納めたことでここを岩蔵と呼ばれるようになったと伝わる。新編武蔵風土記稿にも疝気(せんき)や骨折、打ち身に効くと記し、古くから湯治場としてにぎわった。御岳山上にある武蔵御嶽神社へ詣でる御嶽講の人々も上州(群馬県)や武州(埼玉県)方面からやってきて岩蔵温泉で一休みした。

儘多屋の向かいに湯乃権現社を祀っている。ここは村の行事とは別格に草鞋が掛かっていた。権現社の中に地元の人々が湯壷井とか、契の湯と呼んでいる深さ140㎝、直径125㎝の湯井を収めている。最盛期の昭和のころは軒を連ねるようにあった5軒の宿が連日のようににぎわっていた。なにしろ都内唯一の温泉郷だったから。
儘多屋は、漢方医だった儘田長松(埼玉県本庄市)が明治5年(1872)ごろに開業した。多摩めぐりの一行が訪ねた日は、法事などを行う家族連れが次から次へと玄関に入って行った。参加者の中には「4回も来た。懐かしい」「一時は毎年忘年会をして大騒ぎした」と思い思いに往時を振り返っていた。


縄文人も暮らした岩蔵
四方八方が小高い山に囲まれている岩蔵温泉郷南方にある高台のてっぺんには「岩蔵住居跡」(青梅市指定史跡)があった。この地を地元では「上の台(うえんでい)」といっている。奥まった所の緩やかな窪地で縄文時代中期の人々が暮らしていた。いま、切り拓いた畑地には草が一本もないと言いたくなるほど手入れされていた。いまも畑を耕すくらいだから日当たりは抜群だ。下ってすぐに黒沢川が流れており、水にも恵まれている。この竪穴で笑い、語り合った縄文人の笑顔を思い描いた。

住居跡発見から同市の史跡指定までの経緯は、こうだ。昭和39年(1964)、表土から1m下で焼土が発見された。翌年、青梅市文化財保護委員会のメンバーが現地に入った。その結果、3つの竪穴住居跡のほか、勝坂式と加曾利E式土器や石斧、黒曜石を含む石鏃が多数確認された。いずれも縄文時代中期(4千~5千年前)の遺跡と断定された。3号住居跡の一部は切り崩されていたが、4つの柱穴や縁石で組んだ炉跡が原型を留めていた。青梅市では昭和41年(1966)史跡に指定した。


20年間採炭した東京炭鉱
のびやかな丘陵を下り、小曽木街道へ出た。ほどなくして目に着いたのはバス停「東京炭鉱跡」の大きな文字だった。東京に、炭鉱なんて、あったのか? この地で昭和35年(1960)までの20年間、亜炭と泥炭を採炭していた。
亜炭は一般用の暖房燃料として昭和24年(1949)まで採炭、その後は固形燃料の増量粘結用として日本燃料(株)へ販売した。一帯は黒沢川が運んだ草木が泥土と混ざった層炭地で、この層の厚さは平均1m、広さは2千aに及び、埋蔵量は24万tと推定されていた。昭和30年ごろの月産は350~400tで、40人ほどが採掘に関わっていた。

立坑は40m、坑道の延長は約150mもあった。昭和31年当時の炭鉱配置図を見ると、掘削中の排気口や電気室、鍛冶場もあり、広範囲に設備を施していた。産出した亜炭や泥炭は巻き上げ機で搬出した。さらに80m先までワイヤーで引いて乾燥場へ運んだ。乾燥は天日干しだった。この後、泥炭を粉砕機にかけて筵(むしろ)を二つ折りにしたカマスに詰めてトラック輸送していたという。亜炭も泥炭も家庭の暖房用や煮炊きに欠かせない燃料を東京で生産していたことに驚いた。現代では遠くなった生活史の一つになってしまったが・・・。

斜面に張り付く神社
小曽木街道の西方、岩蔵と古武士(こむし)境の民家にもあったフセギ行事の草鞋を見た後、たどり着いたのは、きつめの斜面に張り付いていた小曽木御嶽神社だった。ここの神楽殿は毎年7月下旬に行われるフセギ行事の草鞋作りの会場だった。社殿は真新しい。

神社の伝承では日本武尊が東征の折に勧請したという。また寛平年中(889~897)に勧請した、奥津宮と呼ばれていた御嶽蔵王権現が北方の山頂にあったが、安永年中(1772~80)に山火事に見舞われて炎上。同5年に本社に合祀されたという。現在の社名に改称したのが明治3年(1870)。3年後、村社になった。祭神は天穂日命(あめのほひのみこと)。ご神体の銅製懸仏(蔵王権現、十一面観音)は青梅市有形文化財。
御嶽神社の隣にある石倉(せきそう)禅院は曹洞宗で金峯山と号している。寛永年間(1624~44)に開山されたが、明治6年(1873)の廃仏令で焼失。再建されたのは昭和41年(1966)。無住の禅寺で山間の静寂さに溶けていた。
扇状に立つ日本武尊伝説の大岩
禅寺の裏手に回る格好で山中に入り、行き止まりの林道を歩いた。味藤さん曰く「青梅と江戸を結ぶ古道で青梅街道の原型を物語る道だ」そうだ。歩くこと10分余り。忽然と荒々しい岩肌の壁が山道に迫り出すように立ちはだかっていた。高いところで20mほどか、岸壁は扇型に広がり、その長さは100mもあるだろう。地元の人たちは「大岩」といい、岩蔵の日本武尊伝説にいう岩蔵と見られている。 この岩は、海底に堆積していた石英質の殻を含み、色は黒や灰色などで構成しているチャートだ。青梅市内の地層は東から西へ向けて成木層、雷電山層、高水山層、海沢(うなざわ)層に分類されており、いずれも中生代(約2億2500万年前~6500万年前)のもの。大岩を構成している成木層は北小曽木断層の北東側に分布している。砂岩や頁岩(けつがん)から成り、石灰岩やチャートをレンズ状に挟んでいる。江戸時代に石灰を掘っていた近くの上成木村あたりでは直径100m前後より狭い範囲だそうだ。

狭山丘陵の北に立川断層がある?
岩蔵地区に大岩の露岩があることについては、立川断層との関連が説かれている。立川断層は、飯能市原市場から青梅市域に入り、中里-岩蔵-笹仁田(ささにた)峠-七日市場-水窪公園を経て、瑞穂町長岡長谷部や箱根ヶ崎・狭山池を通り、南東の立川市、府中市域までの33kmにわたっている。数十万年単位で活動している都内唯一の活断層と従来は推定されていたが、東京大学地震研究所が平成24年(2012)から3年間に行った大規模な調査で狭山丘陵から南域に断層がないと結論を出した。
このことから成木、小曽木を含む青梅市域から北側には活断層の存在が否定されなかったことになる。以後、箱根ヶ崎から北側では「箱根ヶ崎断層」に改称する動きがある。
大岩から東南東650m地点にある岩蔵温泉の地中には立川断層があることになる。温泉といえば、一般的に地中の断層面に沿って地下水が上方へ湧いてくる。その水温が高かったり、特定成分が多かったりして温泉になる場合があることから岩蔵温泉は、そんな地形・地質の環境下にあることを認識した。それだけに大岩の中央付近には地震計測器が設置してあり、また、大岩に寄せるように吊るしてあるフセギの草鞋を見て昔の人々の災いを思う気持ちに触れ、草鞋に手を合わせた。帰りの小曽木街道沿いの岩蔵・富岡境の境沢橋にあった6つ目の草鞋にも平安を期した。
【集合:3月23日(日)午前9時45分 JR青梅線東青梅駅北口/
解散:東青梅駅北口 午後4時ごろ】
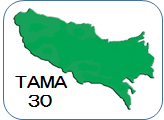 多摩めぐりの会
多摩めぐりの会