昭和13年(1938)1月25日、青梅電気鉄道(立川-御嶽間)18番目の駅・停車場として生まれた「昭和前仮停車場」。いまのJR青梅線昭島駅(昭和34年10月1日改称)の前身だ。駅北口界わいの土地約130万㎡を所有する航空機製造会社の昭和飛行機工業(株)が土地や資金を提供して設置した。いまも北口駅前を中心に同社が所有する土地面積は、東京ドーム28個分に相当する。
ここにイトーヨーカドーはじめ、トイザらス、MOVIX昭島、アミュージアムなどを一体化して「モリタウン」と総称している。ほかにケーズデンキ、カインズホーム、ハーレーダビッドソンなども連なる。多摩西部域の中核都市として新しい町並みを作っている。

敷地内に長さ200mに渡って設けられた「切り株道」などトレイルレーンもある
駅北口から北へ延びる通りを進むと、目を見張る光景に出くわした。左手に高さ16.5mのクライミングウオール、右手にスピードウオールの壁が出現する。思いもしない光景だった。これぞ、青梅線駅前の新しい顔だと飛びついた。平成27年(2015)にオープンした。

頭上に覆いかぶさるクライミングウオール。その前の池で子供がカヌーを楽しんでいた
ウオール一帯をモリパーク・アウトドア・ビレッジと名付けている。約2万2千㎡の敷地にアウトドアに関する物販店、飲食店、クライミングジムなど15店舗が入る7棟の建物は、いずれも1階建て(一部2階建て)で空が一層広く感じる分、眼前にそそり立つウオールが異様に高く見える。ウオールは、国際競技基準に則った作りで、ワールドクラスの大会開催が可能だという。
スポーツクライミングは、来年開催予定の東京オリンピックで初めてオリンピック種目に採用された。競技の元は登山だ。頂上を目指す手段の岩を登る技術が時代と共に高まった。ただ単に頂上に立つ目的ではなく、岩壁を登ることそのものを楽しむロッククライミングが欧州で育った。ロッククライミングではパラコード(ロープ)やカラビナ(金属製の環)、ハーネス(安全ベルト)など様々な道具を使う一方、フリークライミングは、身の安全確保を最小限にした体一つで登るスポーツで1970年ごろ、欧州で広まった。80年代には人工壁が登場して引き付けられるアスリートが多くなって89年以来毎年、ワールドカップが開かれている。

難度が高いクライミングウオール。オーバーハング状の壁にも果敢に挑む
競技は3種目の複合で争われる。ボルダリングは、巨石に見立てた出っ張りがある壁のボルダーコースに挑む。ボルダーは配置や傾斜角度が異なる複数の巨石に選手が1人ずつ挑む。高さ5m以下に設定されたコースをいくつこなしたか、その数で勝敗が決まる。途中で落ちても制限時間4分以内なら何度も挑戦できる。見どころは、ジャンプして片手でボルダーをつかむテクニックだ。
2つ目の種目はリード。高さ12m以上のコースを制限時間6分でどこまで登れるかを競う。不規則につけられたホールドを瞬時に効率の良いルートを選択して手と足の位置を決めて攻略する。安全ロープを身に着けているとはいえ、手の指や腕、足に負担をかけすぎると手足が震え、先へ進めなくなる。一度落ちたら競技はお仕舞いだ。

スピードウオールに繰り返し挑む若者
もう1つの種目はスピード。高さ15m、前傾5度の壁のトップパネルを1秒でも早くタッチすることだ。同じ条件の壁を2人ずつで対戦するトーナメント方式で戦う。熟練男子クライマーなら1秒でビルの1フロアに相当する2~3mを登るそうだ。テレビCMにそんなシーンがあったのを思い出す。
身を守る3点確保は、岩登りもフリークライミングも同じだ。フリークライミングで威力を発揮するのがシューズだ。靴底で巨石や突起物をしっかり捉えられるようにつま先が固く、土踏まずから先が下に向けて反っている特別仕様だ。
どの競技も滑り止めのチョークの粉を手に塗って壁に向かえば登れるというが……。全身をバネにして手で巨石やホールドをつかんで、限りなく負担のないコースをどう編み出して登るかが勝敗の分かれ目だ。瞬発力も持久力も求められる。

ニョッキリ立つ前傾5度のスピードウオール。ウオーミングアップも入念だ
この日、スピードウオールに挑んでいた20~30歳代とおぼしき男女5人がいた。見た目で前傾5度の壁は垂直に近いが、壁に挑む人には相当なオーバーハングに感じるだろう。1人が壁に挑む直前、足腰を整え始めた。手につかんだチョークの粉を手全体に塗りこめながら壁の上段を見上げる。ルートを探っているのだろう。第1歩の左足をホールドに置き、そして、両手を延ばす。一気に上に向かって直線的にホールドをこなして行った。目まいしないのか。怖くはないのか。クライマーズハイの面持ちか。サルのような身軽さだ。トップのタッチパネルを叩くまでに1分もかからなかっただろう。見ているだけの私は、トップから見回す街の眺めを想像するしかなかった。
一方の手馴れない挑戦者は、高さ2mほどの地点で左に寄ろうともがいているうちに宙づりになって「あ~」と悔しさが滲む声を発して着地を余儀なくされた。仲間たちは、繰り返し壁に挑んでいた。
私は、1時間以上も彼らの動きと壁を見つめていた。飽きなかった。が、自分も挑んでみようとは、寸時も思わなかった。最近、周囲から高齢意識を刷り込まれている中、評論家の樋口恵子さんがいう“ヨタヘロ(ヨタヨタ・ヘロヘロ)期”に感じるところがあるから無理もなかろう、と苦笑した。
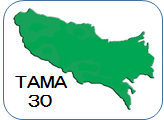 多摩めぐりブログ
多摩めぐりブログ