東久留米市柳窪4丁目に、古くからこの土地の鎮守社として人々の信仰を集めている天神社が建っている。天神社の創建年代は不詳とのことだが、柳窪(柳久保と書くこともある)の開村が寛文10年(1670)であることから、寛文年間前後の創建と推察されている。

「柳久保小麦」の誕生
この天神社の境内に「柳久保(やなぎくぼ)小麦」について語る説明板が立っている。

説明板には
麦は米とともに重要な主食であると同時に、味噌などの原料でもあり、かつて冬の東京の畑は一面が麦畑でした。
小麦の品種「柳久保小麦」は、嘉永4年(1851)、現在の東久留米市柳窪の奥住又右衛門が旅先から持ち帰った一穂の麦から生まれたといわれています。
優良な小麦だったので評判となり、「又右衛門麦」あるいは「柳久保小麦」と呼ばれ、東京各地や神奈川県などの近隣県の農家でも栽培されました。
この麦からは良質の粉ができ、うどん用として大変人気がありました。また麦の背丈が長いので麦藁は農家の「わら屋根」にも利用され重要な品種でした。こうして、この麦は長い間栽培が続けられていましたが、昭和17年(1942)でその姿は消えてしまいました。
現在、「柳久保小麦」のタネは農林水産省生物資源研究所に保管されています。
JA東京グループ
と書かれている。
「柳久保小麦」が誕生した柳窪は、黒目川の源流近くに開かれた村で、八代将軍徳川吉宗の武蔵野新田開発によって享保年間(1716~36)に柳窪新田へと発展して行った。
麦類は乾燥と寒さに強く、田畑の裏作として栽培できるため、柳窪村をはじめ武蔵野台地の人々にとって重要な作物だった。冬の畑は緑で被われていたという。
当時、麦は米にまぜて炊く大麦と、粉に挽いてすいとんやうどんにする小麦が栽培されていたが、大麦が入ったご飯よりも口当たりが良いうどんの方が好まれたという。
そこへ、嘉永4年(1851)、柳窪の奥住又右衛門が旅先から持ち帰った小麦を栽培してみたところ、良質の粉ができ、美味しいうどんが仕上がった。又右衛門の麦は「柳久保小麦」と評判になり、東京のみならず近隣県の農家へと広まって行った。
「柳久保小麦」が好まれたもう一つの理由は、麦の背丈が長い(120㎝~140㎝)ことから、カヤ野が少ない地域では農家のわら屋根に好都合で人気を博した。
しかし、時代とともにわら葺屋根が少なくなり、さらに「柳久保小麦」は背丈が長いので雨風によって倒れやすいことや、太平洋戦争が始まり食料増産の声の高まりによって、背丈が短く栽培しやすい品種へと代わって行った。「柳久保小麦」の栽培は昭和17年(1942)までに途絶えた。
時は流れて、昭和60年頃、「柳久保小麦」の復活をめざす人物が現れた。
「柳久保小麦」の復活
「柳久保小麦」の復活をめざしたのは奥住家の4代目に当たる奥住和夫氏で、和夫氏は農林水産省生物資源研究所から「柳久保小麦」のタネを譲り受け、栽培に挑み成功させた。しかし、収量が少なく、背丈が長く倒れやすいことから他の生産者には広まらなかったという。
その後、「柳久保小麦」を町おこしに結びつけるため、栽培を広げようという機運が東久留米市、商工会、農家の間で高まり、平成15年(2003)に賛同した農家が栽培に取り組み始めた。平成19年には、「東久留米柳久保小麦の会」が発足、今日に至っている。
収穫間際の柳久保小麦 11月下旬頃種を捲き、翌年の5、6月頃収穫
収穫される小麦の収量は低いとのことだが、「柳久保小麦」の小麦粉はうどん、ラーメンをはじめ、かりんとう、パン、菓子類の原料として、主に東久留米市内の飲食店や販売店へ納められているという。
東久留米市役所1階のカフェで、食数限定ながら、ランチタイムにうどんを提供しているという情報を得たので出かけてみた。早速、手打ちうどんを注文(700円)。 運ばれてきたうどんは、一般のうどんよりも太めで小麦の生地の黄色みが出ている。つゆは羅臼昆布と鰹節を出しに仕上げたそうで、中に下ゆでして余分な脂を落とした豚肉が数切れ入っている。薬味には、ホウレンソウ、ショウガ、ネギが添えられていた。 「柳久保小麦」を用いたこれらの献立は、武蔵野地域に古くから伝わる「糧うどん」の本来の姿を再現しているのであろう。

つゆに浸して口に含んだ麺は、ややコシが強く、ショウガの香りとともにうま味が口中に広がった。
かつて、武蔵野台地に深く根付いて農家の大切な作物となった「柳久保小麦」、その「柳久保小麦」を用いた手打ちうどんを味わえたことに満足してカフェを後にした。
参考資料
・江戸・東京農業名所めぐり JA東京中央会
・江戸時代の小麦品種を現代に受け継ぐ 農林水産省
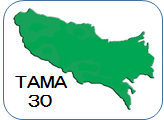 多摩めぐりブログ
多摩めぐりブログ 
