
水がなく、萱(かや)が広がるばかりの武蔵野台地の光景を、京都の都の人々は月光に浮かび上がる平原と、その彩光にきらめく多摩川(玉川)と大地の広がりを演出するかのように富士山を抱く絵模様の武蔵野を思い描いていた――玉川上水が開削されて水を得たのは武蔵野台地に新田開発をしたからだ。その開発によって一変するかのように植生が変わった。人による開発の手は村や町を変え、その煽りで雑木林へと植生が変わり、景観を変えてきた。雑木林に人の手が入れば、植生は持続するが、雑木林に人の手が入らなくなると、小刻みに変化し続けて、シイノキやシラカシなどの常緑樹に様変わりして生物多様性がない暗い林に姿を変える。そのサイクルは500年から1千年という長いスパンだ。8月1日、武蔵野プレイスで開いた多摩めぐりの講演会で、樹木医で元日本樹木医会会長の椎名豊勝さんが語った。椎名さんは「武蔵野植物の移り変わり」について万葉の時代から今日までの長い時空で武蔵野の植生がどのように変遷したのか、都人は武蔵野にどのように憧れていたのかを史実や万葉集、古今集、更級日記などに綴られた都人の思いとともに、その遷移を語った。参加者50人へのプレゼントは紅葉したコナラの葉で椎名さんが手作りしたストラップやしおりにもなるおしゃれな一品だった。講演の概要は、次の通り。
しいな とよかつ 昭和19年(1944)生まれ。品川区に育ち、東京農大造園科学科卒業。
昭和43年(1968)東京都に入都。大田区公園課長をはじめ、国際花と緑の博覧会協会企画調査課長として会場企画・造成・管理に携わる。
平成2年(1990)恩賜上野動物園工事課長でゴリラ、トラが棲む森を造成。葛西臨海水族館を立ち上げる。
平成10年(1998)東京都都市計画局公園緑地計画課長。東京都景観条例を作成。その後も公園や緑化事業に携わり、国営昭和記念公園を運営管理する財団法人公園緑地管理財団昭和管理センター長などを歴任。昭島や小平、小金井、西東京市、新宿区の緑化審議委員を務めている。生活周辺の植物に焦点を当てた「園芸ゼミ」を読売新聞多摩版に連載中。昭和記念公園自然観察ツアーのガイドを務める。

アカマツに覆われていた狭山丘陵
東京近辺であれば、最初はシイノキの密生林です。次は萱の原。アカマツ林も今はない。明治初年ぐらいになると、狭山丘陵はほとんどがアカマツだった。雑木林が進むとシイノキが伸びる。この繰り返し。
こういう雑木林などの代表的な植生が移り変わって行くのを植生遷移という。この移り変わった理由と、どんなものが新たに出てくるのか。小金井公園の小金井桜の根本にはイチリンソウ、ニリンソウがある。玉川上水に架かる陣屋橋は新田開発の時に陣屋を置いたところで、川崎平右衛門が手下を常駐させて新田の生活を見守っていた。その陣屋橋のそばに草本類が出ている。花の大きい方がイチリンソウ、もう一方はニリンソウ。
都と異なる武蔵野の地形
最初は多摩と武蔵野を見ましょう。武蔵国分寺とか、府中には国衙(こくが)があった。武蔵国の県庁所在地みたいなもので、その中心地が府中の大國魂神社周辺。そこに役所が集中する国衙があった。馬場大門から大國魂神社へ向かって左側に入ると、国衙の柱を再現している。もう一つ武蔵国の国分寺も重要なポイント。国を治める国分寺と国分尼寺があった。武蔵国という大国を象徴する伽藍だ。
武蔵野台地とは、国木田独歩はこう言っている。武蔵野台地は、雑司ヶ谷から板橋の中山道を通って川越へ達し、入間、立川あたりを指す。多摩川を限界として、川崎、上丸子とか下目黒に入る西側。東は杵川。独歩は隅田川の向こうの江東地帯も入れている。「この範囲に異論があれば取り除く」ともいっている。一応私は取り除いて考えている。
武蔵野台地は、南が多摩川、西が入間川、北が荒川に囲まれた地域を指すことが多い。この地域は青梅市を扇の要とする多摩川が作り出した扇状地。武蔵国の中心地が多摩郡だった。全体はほぼ四角形。京の都は東西方向で29km、南北で49kmに位置して三方が山に囲まれている。北山、東山、西山と。高低差では高尾山ぐらい。都の平安京は東西4.5km、南北5.2kmとかなり狭い。京都盆地であり、その中に桂川、宇治川、鴨川が流れていて、変化に富む地形を作っている。平城京は奈良盆地にあり、東西方向25kmから30kmであり、南北に長い。大和高原が標高400から600m。生駒山が640m。三方が山に囲まれて、その盆地に大和川と木津川の支流が発達して都を形成している。
見渡す限り同じ植物が繁茂
京や奈良の都と武蔵野とは、何が違うかというと、多摩には水がない。さらにどこまでも平らで、その長さは南北40km以上、東西50km以上にわたる。東、北には100km以上も山がない。丘陵も存在しない。見えるのは北方の筑波山ぐらい。この光景は昭和記念公園の花みどり文化センターに立つと分かる。南と西側には大山から始まって丹沢山地があって、富士山が奥に立つ。奥多摩の峰があって、埼玉の正丸峠まで連山になっている。北と東には何もない。それに水利の悪さが重なる。この台地に川は流れているが、例えば野川。京都の鴨川に比べたら、大分違う。それから石神井川、黒目川とか、埼玉県境の柳瀬川とか、その程度。ある標高までのところに湧水が出ないとダメ。
なぜこの3つの都市を比較したかというと、この光景は、我々にとってなんでもない普通の世界。山に囲まれている狭い盆地で暮らす平城京、平安京の都の人にとって武蔵野は、新鮮な驚きであったのは言うまでもない。彼らは奈良の春日野とか、京都の嵯峨野、紫野に比べても、そこはそんなに広くない。そこには富士山という高い山もないし、月も白雲も見渡す限り同じ形態の植物が繁茂している風景ではなかった。平安時代以前の武蔵野は、すでに萱の原だった。
武蔵野の地形にも触れましょう。武蔵野台地を形成する荒川低地。その間に大宮台地がある。これらは標高20mぐらい。今皆さんがいるここら辺りで60mぐらいかな。井の頭公園あたりで50mぐらい。西が武蔵野台地、多摩川に沿うように台地になって、国分寺崖線、立川崖線などがある。大体は多摩川が作った河岸段丘。西は入間川。今あげた範囲が武蔵野台地。
武蔵野台地の元は青梅。東に延びるのが狭山丘陵。北側に黒目川、東に石神井川が流れる。こういう関係で武蔵野台地は扇状地で、富士山と浅間山の火山灰が堆積してできた。その間に多摩川が蛇行して奥地から砂利を運んできた。そこに何回も富士山が噴火して、さらに多摩川の蛇行などでローム層と礫層のサンドイッチのような地質構造を形成した。

新田開発で生まれた雑木林
どのように武蔵野のイメージが変わってきたか。風景は、ほとんど植生が作っているから、最初はシイの密生林、次は萱の原、牧草地。それから江戸時代に入ってちょっと経つと新田開発で雑木林が生まれた。明治に入ると近郊農業が盛んになった。大正・昭和には都市化が進み貴重な緑となったという流れがある。
風景をイメージとして点描すると、最初は未開の地。それから野草、月の名所の後は農村風景。さらに国木田独歩らが活躍して武蔵野の魅力を多くの人々に知らせることになった。ここら辺が明治時代の風景である雑木林とか、貴重な存在になって、現在では、その生物多様性、雑木林と林床の草本も含めたトータルな生態系で見ていきましょうという社会的視点になった。
万葉集とか、古今和歌集、江戸時代になると、江戸名所図会などに武蔵野の風景が取り上げられて、明治になって国木田独歩が「武蔵野」を編んで、徳冨蘆花らが武蔵野に着眼した。最近では雑木の庭とか、里山林が注目されている。これが10年ぐらい前ですから丁度、生物多様性が叫ばれた時代に重なる。
あとは開発の関係ですね。最初は野焼きとか、馬の放牧、それから玉川上水の開削、新田開発、電車・鉄道の敷設と続く。大正期に入って関東大震災、昭和になって太平洋戦争、戦後の復興というように時代が流れた。さらに都市計画法とか、生物多様性条約の問題も発生してきた。
1千年サイクルで植生変わる
植物は放っておけば、変わる。放りっぱなしにすると、どんどん変わってしまう。500年以上のサイクルかな。人生100年ではとても叶わない。
1番最初がどれかわからないけれど大体、スダジイの極相林だね。やがて森は常緑樹でクライマックスになる。これは安定している。数百年維持するといっているので1クール1千年ぐらいかかるかな。多摩地域がその一番安定していた状態というのはシイの木。今もあちこちに残っている。神社へ行くとシイの木の大木が見られる。
武蔵野ではスダジイが優先している。沿岸部ではタブノキになる。タブノキで残っているのは恩賜浜離宮庭園。今が一番安定期の状態。山火事とか、倒木、野焼き、焼畑の後を放置すると、イネ科植物が代わって芽を出すのが最初はチガヤとか、イネ科の一年草、ススキなどの草が全面に繁茂する。皆さん、休耕田を見るとわかりやすい。水も入れないで放っておけば、土が乾いてチガヤぐらいしか発芽しない。自然湧水のあるところには、また違うアシやガマに世代交代が進む。武蔵野は水がないから、まさにこんな風景になる。もうちょっと発達するとススキが増え、ススキなどの草原になる。
要するに人為的な行為である野焼きや焼畑、放牧とか、秣(まぐさ)採りを続けておれば、この遷移がストップされる。例えば馬などの放牧を例にすると、飼料としての秣採り、焼畑農業のための野焼き。あとは狩り、火田(かでん)狩猟といって火を放って動物を追い出して捕まえる狩猟のこと。この繰り返しによってススキの原が維持される。
アカマツが育ってくると、根本にススキはあるけど、上の方はアカマツ。アカマツは痩せた土地で育つ。アカマツは、もう今はないですけど。それからクルミ、コナラというふうに土地が肥沃化して、さらに萌芽更新で遷移するのを人為的に下草刈りとかで止めている。それが今見えている雑木林の状態。人の手が入らなければ、ぐるぐる回って1千年ぐらいのサイクルで繰り返すかな。
昭和記念公園と残堀川の間にあるスダジイは、武蔵野最古の森の風情です。スダジイの木の下にはほとんど草本がない。落ち葉だけ。何が発芽するかというと、常緑樹の実生。例えばシイの木の実生。要するに暗くても成長できる樹木が生えてくる。ギンナンなども出る。焼畑農業とか、火田狩猟とか、野焼きをして森林を切り拓くのは人類の歴史はどこも同じ。
日欧と違う暮らしが反映
だが、生活の違いによる日本とヨーロッパの森林の形態が異なる。ヨーロッパにも森林はあった。ヨーロッパは肉食と羊毛で暮らしている。衣類を作るのに日本は綿とか、麻とか。絹だったら繭でしょ。繭だったら家産の蚕の場合はクワ。クワの葉っぱを敷き並べてやるくらいだから、ヒツジの飼育とは違う。羊毛だったらヒツジを野に放って勝手に食べさせる。食事もヨーロッパでは主に牛とか牛乳とかだからヨーロッパには森林がなくなっちゃった。
ただヨーロッパは自然の再生力がすごく弱い。日本は温帯モンスーンで雨が多く降るから、ここが違う。ヨーロッパは自然の再生力が少なくて、綺麗な草原になってしまう。イギリスではヒツジがいて牧場がある。あの風景は人間が作ったもの。食生活とか、衣類に代表されるように日本とは生活スタイルによる違いが風景を異にしている。
繰り返し言っているように武蔵野の風景は萱の原。京都は違う。川がいっぱいあるから田んぼを作っている。
植生変わらない焼畑農法
武蔵野では田んぼができないんですよ。後で出てきますけど。ススキだとか、生い茂る萱の原から自然開発による雑木景観へと変化した。要するに江戸時代に大々的に行われた新田開発でそうなった。新田開発して生まれたのは水が引かれたから。
水がないところで何が成立したかというと、おそらくこんなイメージだった。「武蔵野は数百里の平原にして月光万里玉川に及び富士の嶺を照らし無双の勝景」と詠まれた。素晴らしい景色だけど、人が住むところじゃない。そこには火田狩猟という人為的行為が加えられた。この田を燃やすと獣が出てくる。イノシシとか、シカとか。それを例えば穴を掘って罠を置いて生け捕りにした。武蔵小金井駅南口の再開発で見つかった遺跡は動物の落と穴だった。この穴に尖らせた杭を入れて、火田狩猟でおびき寄せたシカなどの動物を落として食べた。火田狩猟で得たのは動物の肉だけでなく、肥料の成分であるカリウムを焼畑農業に使用した。この作業も5年ぐらいのサイクルで焼く畑を移していく。武蔵野は、秣採りや定期的な野焼き、放牧による新芽の摂食、刈り取りによってススキの原で止まった状態になっていた。このことで武蔵野の植生は江戸時代の新田開発まで1千年以上続いたと推察される。
地形と水の関係は、どんなふうだったかいうと、北には狭山丘陵、国分寺崖線、府中崖線、立川崖線、昭島崖線があり、それぞれの縁には湧水が出る。だから多摩川との間に田んぼができて、稲作が可能になった。弥生時代から田んぼができていた。狭山丘陵の麓でいえば、やっぱり湧水が出る。湧水は空堀川とか、柳瀬川、黒目川とか、この流域に住んで馬を放牧して、焼畑農業や火田狩猟で生活を立てたのが武蔵野台地。多摩川水系と荒川水系の分水嶺でもある。これら以外の水のない地域の武蔵野台地に水を取り入れることができたのが玉川上水の開削だった。
人が埋もれる蘆の原の大地
立川の砂川とか、小平の小川あたりは、1650年代に新田開発された。その頃の町は、現在の青梅街道沿いの田無の場合、町の機能があった。甲州街道沿いの府中や高井戸といった古い村には本宿とか、駅などがあった。崖線の麓には古くからの村があり、多摩川の際に点在していた。武蔵野台地の萱の原はこういうところにあった。地形的にも馬の飼育には良い場所で勅旨牧があった。いまで言えば、国営牧場みたいなものでしょう。近世になると府中の馬場大門が生まれた。
要は餌になる草の生産地だったわけ。夏から秋は放牧して、冬から春は周辺の山野に放すのが一般的な飼育だったらしい。そのためには馬の放し飼いが可能な広い野が必要で、周囲に障害物があって馬が逃げにくい場所だった。それ故、馬の飼育によって培った騎馬技術とか、さらに狩猟による戦闘技術が高い武蔵武士の勇猛ぶりは坂東武者であって、その名は都に鳴り響いていた。だから防人に仕された。九州太宰府の防人は京都や朝廷の衛士になった。結論的に言えば、乏しい武蔵野の水利で、田んぼの耕作は限られる。馬を育て、狩猟を行い、高い騎馬技術を持ち、戦える武士が存在していた。それを支えたのが武蔵野の萱の原だった。
都の人がどんなふうに武蔵野を思っていたか。武蔵野はほとんど人が住んでいないから誰も何も感じていなかったと思う。住んでいる人は、その風景や実態しか知らないんだから。でも、京都では違ったイメージで捉えられていた。11世紀に編まれた「更級日記」では菅原孝標の女が詠むには『今は武蔵野の国になりぬ。むらさき生ふ(おう=生え延びる)と聞く野も、蘆(あし)萩のみ高く生ひて、馬にのりて弓をもたる末見えぬまで高く生ひ茂りて、中を分け行く』とある。14世紀の「とはずがたり」(後深草院二条)では『武蔵の国へ帰りて・・・野の中をはるばると分け行くに、萩・女郎花・荻・芒よりほかにまじるものもなく、これが高さは馬に乗りたる男も見えぬほどなれば、おしはかるべし。三日にや分けゆけども尽きもせず』と歌っている。萱の原から出ることができないくらい高いススキやオギが生え広がる光景を描いている。オギが生えているということは水場があることを示している。江戸時代に新田開発が始まった後も京都で抱く武蔵野のイメージは月が美しい、架空の名所で、ススキやオギ、アシが群生する茫漠たる原野だったようだ。

武蔵野文様生んだエドムラサキ
京都での武蔵野のイメージに野焼きの風景がある。どのようにして作られたか。伊勢物語の東下りの中で、野火に触れている個所がある。在原業平の恋愛もので各段に「昔、男ありけり」で始まることが多く、ある男の一代記を表現している。その中で武蔵野の野焼きが常態化していたと思わせる記述がある。都人は広大な萱の原と、そこを焼き尽くす野焼きが武蔵野の一つのイメージだと思われている。
さらに、これを証明するかのように野火止塚が平林寺にある。この塚を九十九塚とも言う。「野火止塚は火田狩猟による野火を見張ったものか、焼き畑農法による火勢を見張ったものかは定かでないが、野火の見張りであったとする説が有力だという。この種の塚が古くからこの平野の名所になっていて、その名残りを留めていたことでも分かる」という。だが、今となってはほとんど分からない。月のイメージを沸かせるのが戦国武将の太田道灌の武蔵野を詠んだ歌。『里は荒れ 野となる露の 深草や 鶉(うずら)かねやを てらす月影』
ムラサキソウ(紫草)というと京都の人のイメージがある。古今和歌集(905年)の中に、こんな歌がある。『紫の一本(ひともと)ゆゑに 武蔵野の 草をみながら あわれとぞ見る』(詠人知らず)。この花はその後、一躍、武蔵野の名花になった。万葉集にはムラサキを結びつける歌はない。要するに紫は、日本最初の冠位制度(603年、聖徳太子が制定)の冠位十二階の一番上位を示す紫色を指し、称えていた。
歌舞伎の演目「助六由縁江戸桜」に登場するエドムラサキは、江戸時代に登場した文化。薬効があり、今も使われている。花は小さい。ムラサキといえば、井の頭弁天池の弁天様に参道があって、そこに紫灯篭がある。江戸の人口は200万人(諸説ある)。ということは多摩地域がムラサキの産地だった。それで紫灯篭を寄進した。色は、青味がかり、京都の紫とは違う。それが都人にとっては憧れだったのでしょう。今は「幻の花」といわれ、わずかに高尾山近辺に自生しているといわれている。外来種のセイヨウムラサキが入ってきて、厄介者になっている。紫根といってエドムラサキの根から染料を採る。薬にもなるが、セイヨウムラサキは薬にならない。都人にとっては憧れだった。ムラサキの花が一つあるが故に他の草まで哀れと見える。趣き深い。
また、武蔵野のイメージは、日本画定番の絵画構成の一つのパターンになった。杜若(かきつばた)図と同様。これが武蔵野図で『武蔵野は 月の入るべき山もなし 草より出でて草にこそ入れ』などの歌に詠まれて、富士山があって、白雲が浮かび、さらに月が出る。ススキが原にはキキョウ、オミナエシ、ナデシコ、ハギなどの野草が咲いている。これらの光景は屏風絵、扇子、蒔絵、織物にもなって武蔵野文様といわれた。
川と段丘の恵み得た台地
次に水に関する問題も武蔵野では重要。井戸掘削技術は、江戸末期から明治に高まったと言える。それまでは井戸を掘るだけの財力がなかったし、あっても「まいまいず井戸」だった。「まいまいず井戸」は羽村駅前にある。昭和記念公園にも再現した。小平のブリヂストンにもあったはず。津田塾大学の隣にも。それらは埋められたでしょう。埼玉県狭山市には井桁に組んだ石組の「堀兼の井」がある。
青梅から吉祥寺までの約30km区間の狭山丘陵に沿う空堀川の南に延びている武蔵野台地では多くの地点で、水を得る場合、20m以上の深さを掘る技術が必要と思う。水を絶やさないためには、もっと深さがいると思う。井戸掘り技術がこの地に入るのは江戸末期まで待たなければならない。
武蔵野台地でも、いまの23区と多摩郡では井戸事情が異なった。実は23区では地下水5m以下の層が全体を占めているから浅井戸を掘れば水が出た。さらに標高50mぐらいの地点で湧水が多い多摩地域には神田川の井の頭池、善福寺川の善福寺池、妙正寺川の妙正寺池、石神井川の富士見池、三宝寺池、また白子川、目黒川、渋谷川などの侵食でできた解析谷(開析谷)の崖下から湧水が得られていた。武蔵野台地の特徴だね。
多摩川の流路跡である国分寺崖線と立川崖線の南側では、それなりに水事情が良かった。地下5m以下に水の層が集中しているから。武蔵野台地に降った雨が砂利層を透って、崖地から水が浸み出る。さらに容易に水を得られたのは多摩川からの分水。農業用水として田んぼに流入させ、水田が作られた。昔から稲作地帯であったことが想像できる。
狭山丘陵の北側は荒川水系に属する流域になる。所沢市を中心に、その東側の柳瀬川流域や黒目川流域は宙水地帯に当たる。宙水地帯とは、地下水面よりも浅い位置に局所的に溜まっている不透水層であり、井戸掘り技術が乏しい時代であっても浅井戸で水を汲み上げられた。水量が少ないから水田灌漑用水には難しいが、飲料水は確保できた。早くから人が住みついていたことが遺跡からも推察できる。この宙水ではたくさんの人を十分に潤すほどではないが、狭山丘陵の麓は水事情が比較的良かった。立川、吉祥寺をはじめ、国分寺崖線沿いにも宙水があり、小規模の地下水ができる。杉並、中野も多摩の仲間ですね。
小平市ふれあい下水道館で平成23年(2011)から26年に地下水位を実測したら一番深いのが18mだった。3年間の実測結果とはいえ、深さ20mがなければ年間を通して安心して飲み水を得られない。だから水は非常に厳しい状況にあるのが武蔵野台地といえる。
武蔵野が栄えた玉川上水の分水
比較的に安定した水を得られたのは玉川上水を引いてからでしょう。このことが武蔵野植物の生態や景観を変える、大きな影響を与えることになった。
その前のきっかけは天正18年(1590)に徳川家康が江戸へ入ったこと。水が乏しい江戸市中に最初は小石川、次は赤坂溜池を水源にした。1650年代には玉川上水が完成して江戸城の南側まで通水できた。だが、参勤交代で爆発的に人口が増えた。上屋敷、中屋敷、下屋敷ができ、財力がある藩では抱え屋敷を作った。そこに江戸詰めの家臣らが住むようになって200万人くらいになっていた。
市中の水を確保するのに井の頭池を水源にした神田上水や赤坂溜池の水源では足りず、今の玉川上水を完成させた経緯が重要な意味をもたらす。
江戸幕府は財政を潤すためにも新田開発をした。石高を増やして年貢を増やそうとした。享保の改革とはこのことで、いろんな用水を作った。野火止用水は最初からあった。新田開発は、北から上げると、今の小平市、西東京市、武蔵野市、三鷹市、小金井市、国分寺市、立川市に至る。野川辺りから黒目川の南、砂川と小川は1650年代にできていた。
この時代には農政や河川改修などに、身分にかかわりなく民間人を多く登用した。新田開発に欠かせない人物は川崎平右衛門。武蔵野新田の生活安定化の救世主といわれる。利根川の付け替えには伊那忠次が陣頭に立った。その後、平右衛門は木曽三川(木曽川、長良川、揖斐川)輪中、石見銀山の代官も務めた。
武蔵野新田は76村の農家1320軒のうち、曲がりなりにも生活が維持できたのはわずか35軒だった。この窮状を乗り越えるために大岡越前は代官に川崎平右衛門の登用を指示し、まずお救い米を小金井橋で炊き出しをした。これには川崎家の備蓄米を出した。それ以降は平右衛門を武蔵新田世話役に任命し、村に陣屋を構えて農民の生活安定化の経営を始めた。大体10年ぐらいで見通しを立てた。その成果の現れを象徴しているのが小金井桜。
植生を変えた新田開発
新田はどんなふうだったのかというと、農地を短冊型にして入植者を沢山入れようとした。それぞれに屋敷と屋敷林があった。一区画が2千㎡ぐらいあった。それぞれが青梅街道、五日市街道、志木街道、戸倉街道、東京街道、立川街道など街道沿いにあって、玉川上水から取り入れた何本のもの水路を引いて飲み水にした。
それぞれの屋敷林ではケヤキで緑陰を作った。農具の柄などをこしらえるときに使えるシラカシも植えた。屋敷の南側では砂の防塵や遮熱するためにシラカシを高垣にした。さらに北側の奥へはクラフト材になる竹林を植えた。北端の雑木林にはコナラやクヌギ、アカマツ、ヤマザクラなど薪炭や燃料、建材に利用できる木を植えた。畑にはウツギを植えて境界とした。
農家では具体的にどんなことをやっていたかというと、大正・昭和初期に活躍した日本画家・速水御舟(はやみ・ぎょしゅう)が描いた雑木林の絵をみると、雑木林の営みが分かりやすい。冬にかなりの面積の雑木林を皆伐している。ただ、切株を残して春に萌芽更新をさせて次の代を育てていた。残されたアカマツに比べて雑木は幹が細い。雑木は15年から20年ぐらいで伐るのだろう。太いアカマツは何回かの伐採期にも残されていた。家の梁に使うから。
伐採された丸太は太さごとにホダ木、炭焼き、薪用に分別した。さらに粗朶(そだ)も捨てることなく利用していた。例えば竹は建材、竹材、食材。農業用の支柱にも使っていた。杉は製材して板にしたり、燃料にしたりしていた。シラカシは農具の柄、ケヤキは家屋の大黒柱や上がり框(かまち)、臼、太鼓の胴に使っていた。
江戸に200万人くらい人がいるから、武蔵野ではこれらを江戸に供給して生業にしていた。いわば、自給自足の生活の中で自助、共助で成り立っていた。共助は、村で協力したと考えられる。ただ、公助は難しかったでしょう。
元文2年(1737)に始まった新田開発の村おこし策で玉川上水の小金井橋付近に植えられたのが小金井桜だった。大正3年(1914)春にイギリスのアーネスト・ウィルソンが小金井堤に来て硝子乾板写真を撮ったころは桜が元気だったが、戦後は荒れた状態になって、さらに通水が完全停止になり、上水堀の草刈りも行われなくなってヤマザクラの樹勢が非常に衰退した。これが小金井桜の歴史の一端。
時代を先取りした独歩
国木田独歩は「武蔵野」の中で、こんなことを言っている。『冬は、ことごとく落葉し、春は滴(したた)るばかりの新緑萌え出ずる。春夏秋冬を通じ霞に雨に月に風に露に霧に時雨に雪に、緑陰に紅葉に、さまざまな光景を呈する』と絶賛している。この変化する美しさはいろいろな環境を生み出す原動力であり、そこから各種の生きものの生息が可能になる。はからずも独歩は、現代における雑木林の生物多様性の環境を言い当てている。
小金井堤では草本類もよく育つようになってきた。イチリンソウ、ニリンソウ、ワレモコウ、ノカンゾウ、ヤマユリ、ツリガネニンジン…私が思うには、例えばワレモコウの群落は、奥多摩ではともかく、多摩地域は市街地です。ニリンソウの群落の大きさで言えば素晴らしい。小金井桜の下にある。ノカンゾウも6月ぐらいからほぼ全域で咲く。これも素晴らしい。絶滅危惧種がたくさんある。
野火止用水の雑木林も知られている。私が調べた野火止用水の小平、東大和、東村山市などに50種類以上の野草がある。それぞれが雑木林の生物多様性の証明となる。これらにあるのはジュウニヒトエ、ノカンゾウ、ヤブカンゾウ、カリガネソウ、ヤブコウジ、ホタルブクロ、アマナなど。清瀬のあたりにはヒロハノアマナという違う種類がある。
下草刈りをして管理すれば、素晴らしい生物多様性がいつまでも持続できる。常緑樹が入り込んでいるところもあるが、それは植生遷移の途中で、常緑樹はシラカシとかシイの木が芽生えてくる。常緑樹の森になった場合、生物多様性はそれほど豊かではない。
雑木林を残すことで生物多様性が出てくる。うまくすれば150種から200種類ぐらいの草本類が生存できる。今後も生物多様性がある雑木林の必要性を訴えていきたい。
「昭和記念公園自然観察ツアー」紹介
椎名さんが昭和記念公園で植物ガイドをする「自然観察ツアー」は9月から毎週火曜日午前と午後に行われる。公園内とはいえ、植えたものではなく自然発生した植物を中心に見る。椎名さんの予想を上回る植物に出会えることもあるという。「植物はどんどん動いてますから、いつも代役がいます」と期待を膨らませる。園内の植物を1時間ほど観察する。
開催日と観察植物
- 9月 2日 繊細な三島柴胡(みしまさいこ)と蒲(がま)の穂
- 9月 9日 実葛(さねかずら)の雌花・雄花と麻耶蘭(まやらん)
- 9月16日 眩しい藪蔓小豆(やぶつるあずき)と男郎花(おとこえし)
- 9月30日 朮(おけら)の花咲く頃と落雨松(らくうしょう)
自然観察ツアー概要(各日共通)
| 集合時間 | 1.午前の部 10時30分~ 2.午後の部 13時30分~ ※各時間とも開始時刻までに集合 |
| 集合場所 | 昭和記念公園花木園展示棟前 ※JR青梅線西立川駅下車。 西立川口から入場し、みんなの原っぱ手前 |
| 所要時間 | 約1時間 |
| 費 用 | 自然観察ツアーは無料 ※公園入園料は必要 |
※詳細は、観察・ツアー イベント – 国営昭和記念公園公式ホームページでご確認下さい
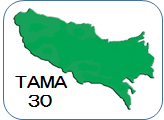 多摩めぐりの会
多摩めぐりの会