マンションに囲まれた谷間で今年も白梅が咲いた。色がない季節を乗り越えて無垢な色映えに魅かれ、開花中に何度も根元に立つのが、この30年の恒例だ。梅雨時に膨らませた果実は色づいて、いつとはなしに枝から消える。路上に落下の形跡がないことから所有者が収穫するのだろう。放置され振り向かれない木ではなく、収穫を待っている人がいることに安堵し、木への労り心が湧く。
多摩地域の梅の名所は、いくつも挙げられるが、子供のころ、梅の花を見に行った記憶がない。いつも遊んでいた近くの常楽寺や稲荷神社の境内に梅の木があっただろうか。いま郷里富山県で観梅の名所に挙げられているのは富山県中央植物園、豪農の館内山邸(以上、富山市)、高岡古城公園ぐらいで、多いところで100本余りだという。
庭先で母が漬けた梅を天日干ししていると夕立に見舞われて急いで取り込んだことが蘇る。「青い梅を食べるな」ときつく言われたことを思うと、梅の木はあったのだ。暮らしに欠かせない梅干しは、いまも食卓に欠かせない。
50年ほど前、青梅市の吉野梅郷を知った。この地の梅博士がいう、梅の園芸種には春日、鶯梅など300種以上あるのに驚愕したものだ。同時に「古事記」と「日本書記」に梅がなく、梅は中国から入った外来種だという。
奈良時代に編まれた漢詩集「懐風藻」に初めて梅が出た。その詩題も侍宴や応詔、遊覧が中心で梅になぞらえて人の情愛を詠んだものが多かった。願望と風流を溶け込ませた梅の形容である百花の魁(さきがけ)は、見方を変えれば、明日の暮らしにしか目が届かない庶民の春を待つ暮らしも詠み込んだといえようか。
暮らしの周りを見れば、梅にまつわるものがなんと多いことか。八重梅、裏梅など100種以上の紋章があり、松竹梅や梅に鶯などの染織がある。400年以上前の「かぶき踊り」が起源といわれる、日本の伝統文化の代表格になっている歌舞伎も梅が舞台を引き締める。「壽曽我対面」などに欠かせない梅の立木といった舞台の大道具を魅せる。職人の手仕事である手ぬぐいがま口の、赤地の梅模様が廓の色気を表現していて華やかだ。菓子に至っては枚挙にいとまがない。
見て由、着て由、食べて由の梅は、生涯の友だ。

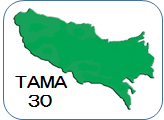 多摩めぐりの会
多摩めぐりの会